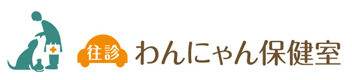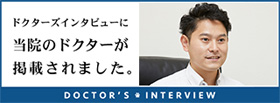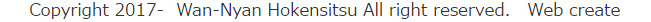肺腫瘍は犬にとって決して珍しい病気ではなく、特に高齢の大型犬では、徐々に進行する呼吸器の異常として現れることが多くあります。今回ご紹介するのは、ゴールデンレトリバーのマコトくん。肺腫瘍と診断されてから半年後、呼吸状態の悪化とともに胸水の貯留が見られ、在宅緩和ケアという選択肢に切り替えました。胸水抜去を通じて、苦しみを最小限に抑えながら、最期の時間をご家族と共に穏やかに過ごしたその記録をお届けします。
肺腫瘍と診断されたゴールデンレトリバーの最後の1ヶ月
マコトくんは、12歳のゴールデンレトリバーの男の子です。2024年9月、かかりつけの動物病院にて「肺腫瘍」と診断されました。はじめは特に目立った症状もなく、通院しながら内服薬を服用し、日常生活を続けていました。
性格は穏やかで、ご家族と一緒にいる時間が大好きな子でした。ご飯もモリモリ食べるタイプで、食欲が落ちることはほとんどなく、少し息が荒くなっても気にせずに過ごしていたそうです。
しかし、診断から半年が経った2025年3月、急に様子が変わり始めました。食欲が突然落ち、呼吸も早く浅くなってきたため、ご家族が再度病院へ連れて行くことを決意。その時、胸水が多量に貯留していることが判明しました。
通院での緩和ケアのはじまり
肺腫瘍の診断を受けた後、マコトくんはかかりつけの動物病院で通院しながらの緩和ケアを続けていました。幸いにも、診断直後の状態は安定しており、無理のない範囲での通院が可能でした。
食欲旺盛だったマコトくんは、内服薬もご飯に混ぜれば問題なく摂取できていました。ご家族も薬の管理をしっかりと行い、日々の体調を細かく観察することで、症状の進行にいち早く気づけるよう心がけていました。
当時のマコトくんは、息が少し荒くなることがあっても、お散歩を楽しみ、日常の生活を自分のペースで送っていました。肺腫瘍という厳しい診断を受けても、ご家族と一緒に過ごす日々が、穏やかに流れていたのです。
ただ、この時期から、少しずつ「呼吸の変化」に注意が必要となってきていました。肺腫瘍が進行する中で、胸腔内に水が貯まることは、よく起こることです。
呼吸状態の急変と胸水の貯留
肺腫瘍の進行に伴い、マコトくんの体調に大きな変化が現れたのは2025年2月下旬のことでした。元気や食欲があったにもかかわらず、急に呼吸が浅く、速くなり、見た目にも苦しそうな様子が目立つようになってきました。
ご家族は、すぐにかかりつけの動物病院を受診し、超音波検査(エコー検査)を実施。その結果、胸腔内に多量の胸水が貯留していることが判明しました。肺腫瘍が進行することで、肺から胸腔に滲出液が漏れ出し、呼吸機能を圧迫していたのです。
その場で胸水抜去を実施することになり、マコトくんはゴールデンレトリバーという犬種の特性もあって、鎮静処置を行わずに処置を受けることができました。この時、抜去された胸水は1500mlにも及び、処置後には呼吸がかなり楽になった様子が見られました。
しかし、ご家族にとって印象的だったのは、処置後の帰宅時のマコトくんの姿でした。行きよりも状態は改善していたとはいえ、大きな負担を抱えての移動であることは明らかでした。この経験を経て、ご家族は「今後は自宅でできる限りのケアを」と考えるようになり、在宅緩和ケアへの切り替えを検討し始めたのです。
在宅緩和ケアへの切り替えと準備
病院での胸水抜去の後、ご家族は移動中のマコトくんの苦しそうな様子に心を痛め、通院に限界を感じ始めました。「このまま通院を続けるのではなく、自宅で穏やかに過ごさせてあげたい」というお気持ちから、在宅緩和ケアが可能な動物病院を探され、当院へご連絡をいただきました。
初診は2025年3月3日。ご自宅の玄関まで尻尾を振って迎えてくれたマコトくんの姿は、まだまだしっかりとした力を感じさせてくれるものでした。身体検査とエコー検査を実施した結果、再び胸水の貯留を確認しましたが、すぐの抜去は行わず、あえて日程を調整し、最も苦しくなる直前で胸水抜去を実施するようにスケジュールを組むことにしました。
また、このタイミングで処方の見直しを行い、鎮咳薬や鎮痛薬を強めに加え、呼吸の快適さを保ちつつ、痛みや不快感をできる限り抑えることを目指しました。マコトくんの状態、性格、ご家族の希望をすべて踏まえて、在宅緩和ケアに向けた最初の一歩を踏み出したのです。
在宅での胸水抜去とマコトくんの反応
初診から4日後、予定通りマコトくんの2回目の胸水抜去を在宅で実施しました。ご自宅という安心した環境で、移動のストレスもなく落ち着いた様子で処置に臨むことができました。この時の抜去量は1380ml。抜去後、呼吸の速さが緩やかになり、ご家族の表情も少し和らぎました。
その後も約1週間おきに胸水の貯留が見られ、次の抜去では1520ml、さらにその次には1750mlと、貯留量は増加傾向にありました。ですが、抜去後は毎回、呼吸が楽になり、短いながらも穏やかな時間が戻ってきました。
胸水抜去は強い痛みを伴うため、処置の可否やタイミングには常に慎重な判断が求められます。痛みの負担と呼吸の苦しさ、そのどちらも極力減らしたいという思いの中で、ご家族と相談を重ねながら、その都度最善と思われる選択を重ねていきました。
最期の時間とご家族の思い
2025年4月7日。マコトくんは、その日も朝まではご飯を食べていたそうです。「ちょっと様子が違うな」と感じたとのことでしたが、その後は静かに、まるで眠るかのように旅立ったとのことでした。
最後まで内服薬もご飯と一緒に食べてくれて、処置のたびに呼吸が楽になり、ご家族とともに少しでも楽に過ごせる時間を作ることができました。苦しみが強くなる前にその時を迎えられたことに、ご家族様も「頑張ってくれたね」と静かに話されていました。
ゴールデンレトリバーのような大型犬では、腫瘍(がん)を抱えることは珍しくないです。呼吸を圧迫する胸水の貯留は命に関わる重大な状態ですが、その都度の丁寧なケアと、ご家族の見守りにより、マコトくんは穏やかに最後を迎えることができました。
胸水貯留の犬における在宅緩和ケアの考え方
胸水の貯留は、肺腫瘍や転移性腫瘍、心不全などさまざまな原因で起こることがあります。貯留した胸水は肺を圧迫し、呼吸を著しく妨げるため、犬にとって大きな苦痛となります。
在宅での胸水管理が重要な理由
- 通院の負担を減らすことで、呼吸状態の悪化リスクを下げられる
- ストレスによる呼吸促迫を避けることができる
- ご家族が側で寄り添いながらケアを行える
胸水抜去の実施タイミング
- 呼吸が速くなる、胸が上下に大きく動くといった症状が見られたとき
- ご飯を食べなくなったとき
- 横になって眠れなくなるとき(座ったまま寝ようとする)
これらの兆候が見られた場合には、胸水の貯留が原因である可能性があり、抜去を検討すべきタイミングです。
胸水抜去時の注意点
- 大型犬では無鎮静で対応できるケースが多いが、痛みは強いということは忘れないこと
- 頻回に抜去を行うと、それ自体が負担になるため、呼吸状態や生活の質を見ながら判断
- 初回の抜去量に比べ、次第に貯留量が増えていくケースが多いため、次の処置のタイミングは柔軟に調整する
在宅で胸水を適切に管理することは、犬のQOL(生活の質)を守り、穏やかな時間を提供する上で非常に重要です。
次は、当院が行う在宅胸水抜去と継続的なケアの方針についてご紹介します。
当院が行う在宅胸水抜去と継続ケアの方針
当院では、大型犬や高齢の犬に対して、通院や入院によるストレスを避けるため、在宅での胸水抜去を積極的に取り入れています。診察は基本的に獣医師1名で行い、胸水抜去などの処置が必要な場合には、動物看護師が同行します。
在宅での胸水抜去の進め方
- 往診時に超音波検査で胸水の貯留量と状態を確認
- 鎮静なしでの抜去を基本とし、状態によって鎮静を使用
- 初回は処置の反応や量を慎重に観察し、次回以降のプランを立てる
抜去頻度とモニタリング
- 呼吸状態に応じて抜去頻度を調整(例:1〜2週間おき、必要に応じて週1回)
- ご家族からの日常の観察情報も重要な判断材料となる
継続的な在宅緩和ケアの内容
- 鎮痛薬や鎮咳薬など、内服薬の調整
- 酸素発生装置を活用した在宅酸素管理
このように、在宅緩和ケアでは単に胸水を抜くだけでなく、犬の体調やご家族のご希望を踏まえて、柔軟で丁寧な対応を行っていきます。
ご家族とともに過ごした最期の日々
マコトくんが旅立ったのは、2025年4月7日。ご家族に見守られながら、自宅のリビングで穏やかにその時を迎えました。胸水抜去の直後には、呼吸が楽になった様子を見せ、ご飯も少しずつ口にすることができていました。
旅立ちの直前まで見せた“いつもの姿”
- 朝には自分の足で立ち、少しだけお散歩にも行こうとする素振りを見せた
- ご飯の香りには反応し、少量ながら口にしてくれた
- 大好きな場所、リビングのソファー下でゆっくりと眠るように旅立った
ご家族の寄り添いと、安心感
- 胸水抜去の処置も含め、すべてのケアをご自宅で行えたことに、深い安心を感じていただけた
- 「いつもと変わらない日常」の中で過ごせた時間が、ご家族の心の支えに
- 苦しみを最小限にできたことが、ご家族にとって最大の救いだった
在宅緩和ケアの価値
- 病院に行くことなく、最後まで大好きな家族と自分の家で過ごせたこと
- ご家族と獣医師、動物看護師が一緒に歩んだ、最期の時間
- 「家で看取ってあげられて良かった」と語ってくださった言葉が印象的だった
在宅緩和ケアは、ご家族にとっても愛犬にとっても、心穏やかな選択肢となり得ます。
わんにゃん保健室が行う在宅緩和ケアの特徴
わんにゃん保健室は、東京都内および近隣エリアを中心に活動している往診専門動物病院です。ペットの在宅医療、特に緩和ケアやターミナルケアに特化し、「病院に行けない・行かせたくない」状況でも、できる限りの医療を提供することを目指しています。
在宅でできる医療を最大限に
- エコーや血液検査など、病院と同等レベルの検査を自宅で実施
- 症状に合わせた処方変更や、投薬内容の調整が可能
- 緩和ケア・ターミナルケアを熟知した獣医師による診療
ご家族の不安に寄り添う
- 初診では2時間近くかけて、じっくりと問診・カウンセリングを実施
- 状況の整理、選択肢の提示、判断サポートまでを一貫して提供
- 医療面だけでなく、精神面のケアにも重点を置いた対応
苦しまない最期のために
- 胸水や心嚢水の抜去など、症状の緩和に必要な処置も自宅で対応
- 鎮痛、鎮静、呼吸管理など、ペットのQOLを最優先に考えた医療設計
- 家で過ごすこと、家で旅立つことを選ぶご家族への全面的なサポート
マコトくんのように、最期まで“家で”を貫いた子たちの物語が、これからも増えていくよう、私たちはひとつひとつの命と真摯に向き合っていきます。
腎臓病や心臓病、甲状腺機能低下症や甲状腺機能亢進症、糖尿病などの慢性疾患で、定期検診での血液検査や超音波検査(エコー検査)のための通院が、愛犬、愛猫にとってストレスになっていると感じたとき、またはがん(腫瘍)や病末期で、もう余生を穏やかに過ごさせてあげたいと感じた時からは、私たち、在宅緩和ケアに特化した往診専門動物病院わんにゃん保健室までご連絡ください。
残された時間にどんなことを考え、準備していかなければいけないのかなど、1つ1つ生活環境やご家族の意思を確認しながら、緩和ケアプランを構築していきます。
◆-----------------------------------◆
犬猫の往診専門動物病院
わんにゃん保健室
猫の腎不全、末期がん(腫瘍)、診断後の慢性疾患、酸素室設置、家での皮下点滴など、お気軽にご相談ください!
電話番号:03-4500-8701(往診本部直通)
受付時間:10:00~19:00
〒111-0036
東京都台東区松が谷3-12-4 マスヤビル5F
【わんにゃん保健室】
公式インスタグラム、facebookがスタート!