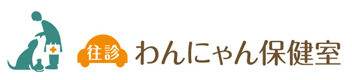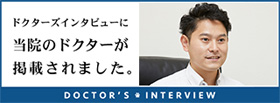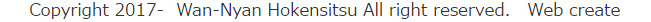大型犬に多く見られる腹腔内腫瘍。診断された時にはすでに高齢で、手術や抗がん剤などの積極的な治療が選択肢に入らないケースも少なくありません。
そんなとき、ご家族ができることは何か——それが「在宅での緩和ケア」という選択肢です。
今回は、東京都渋谷区に暮らす大型犬が、突然の起立不能をきっかけに腹腔内腫瘍が見つかり、ご家族とともに過ごした穏やかな在宅緩和ケアの実例をご紹介します。
犬のがん、特に腹腔内腫瘍と向き合うなかで「何ができるのか」「どう見送るのか」を考えるきっかけになれば幸いです。
目次
- 大型犬の腹腔内腫瘍とは
- 通院が困難な大型犬への往診の選択
- 在宅緩和ケアの開始と治療の進め方
- 終末期に向けた心構えと看取りの準備
- 穏やかな時間の中で迎えた最期
- まとめ:大型犬と家族がともに選ぶ最期のかたち
大型犬の腹腔内腫瘍とは
今回ご紹介するのは、東京都渋谷区にお住まいのご家族と暮らす、12歳・去勢済のゴールデンレトリバー(38kg)、タロくんです。
2025年1月9日の散歩中、突然ふらつく様子が見られたことから緊急で帰宅。その日は特に大きな異常はなかったものの、翌朝には起立不能となり、ご家族だけでは病院への移動が困難だったため、当院へ往診のご相談をいただきました。
超音波検査の結果、タロくんの腹腔内には約8cmの腫瘤を認めました。現時点での画像所見だけでは腫瘍の確定診断はできませんが、年齢や症状から悪性腫瘍の可能性が高いと判断しました。
腫瘍の摘出や抗がん剤といった積極的な治療についてもご提案はしましたが、ご家族としては「手術や入院ではなく、できるだけ穏やかに家で過ごさせてあげたい」との強いご希望がありました。
このように、大型犬の腹腔内腫瘍に対しては、年齢・体力・性格・生活環境などを総合的に考慮した上で、在宅緩和ケアという選択肢をとるケースが増えています。
次は、急な体調変化により通院が難しくなったタロくんに、どのように往診で対応していったのかをご紹介します。
通院が困難な大型犬への往診の選択
大型犬であるゴールデンレトリバーのタロくんは、体調が急変し、翌朝には完全に起立不能な状態となりました。高齢かつ体重のある犬にとって、移動のための介助はご家族だけでは非常に困難であり、移動中の負担も大きなリスクになります。
特に、腫瘍によって出血や貧血が起こっている可能性がある状態では、ちょっとした移動の衝撃が容体をさらに悪化させることがあります。結果として腫瘍が見つかったのですが、この時点ではまだ何も発覚していなかった中での急な症状だったため頑張って通院させようと試みましたが難しく、自宅での診療を希望されました。
当院では、必要な医療機器を持参し、往診で腹部超音波検査・血液検査などの初期評価を実施しました。その結果、腫瘤の存在とともに、炎症マーカーの上昇、肝酵素・膵酵素の上昇、そして軽度の貧血を認め、腫瘍からの慢性的な出血や局所炎症が疑われました。
このように、大型犬で体調急変があった場合には、速やかに往診による評価と対応を行うことが、安全で現実的な選択肢となります。
次は、タロくんに対してどのように在宅緩和ケアを開始していったのか、その具体的な初期対応についてご紹介します。
在宅緩和ケアの初期対応
往診初日に、タロくんの身体検査と血液検査、腹部超音波検査を実施し、腹腔内に8cm大の腫瘤を確認しました。画像と血液検査から判断しても、悪性腫瘍の可能性が高く、また抗がん剤治療や外科手術は希望されないとのことでした。
そのため、タロくんには「在宅緩和ケア」によるサポートを選択しました。これは、残された時間を穏やかに過ごしてもらうことを目的としたケアであり、ご家族にとっても精神的・肉体的な負担を軽減できる方法です。
初診当日は、以下の対応を行いました。
- 皮下点滴による輸液と薬剤投与(鎮痛剤、制吐剤、抗炎症薬)
- 酸素飽和度などのバイタルチェックと全身状態の評価
- 環境評価(タロくんが快適に過ごせる場所の整備)
- ご家族への今後の流れの説明と不安のヒアリング
皮下点滴には、炎症や痛みに対する鎮痛薬、制吐薬、食欲刺激などを含め、その時点で可能な限りのケアを提供しました。
翌日の再診では、検査結果に基づいた今後の見通しと、どのように医薬品を用いながらケアを継続していくのかについて、丁寧に説明を行いました。
次は、定期的なモニタリングとケアの調整についてご紹介します。
定期モニタリングとケア内容の調整
タロくんの在宅緩和ケアでは、1週間ごとの往診を基本とし、状態の変化に応じて柔軟に対応していきました。大切なのは、“今の状態に合ったケア”を提供し続けることです。
定期往診で行った内容
- 身体検査(体重、粘膜色、脱水、呼吸状態など)
- 血液検査による肝酵素、炎症マーカー、貧血の進行評価
- 腹部超音波検査による腫瘍サイズと周囲臓器への影響確認
- ご自宅での皮下点滴内容の見直しと調整
モニタリングの目的は、腫瘍の進行具合だけでなく、症状(痛み、食欲、活動性)の緩和度を客観的に把握することにあります。
皮下点滴内容の調整
最初は皮下点滴を獣医師が対応していましたが、ご家族ができるようにトレーニングを行い、在宅での自立したケアが可能になるよう指導しました。
- 利便性を考えた1回あたりの点滴量の調整(例:30〜40ml/kg)
- 薬剤構成(鎮痛薬・抗炎症薬・制吐薬など)を状態に応じて変更
- ご家族が管理しやすいよう、薬剤の希釈方法や保存方法の共有
症状に応じた細やかな対応
在宅緩和ケアでは、痛みの兆候、呼吸の変化、排泄状態など、細かな体調変化を敏感にキャッチし、対応策を即座に講じることが求められます。往診時だけでなく、LINEなどを用いた連絡体制で、必要に応じて助言や訪問を行いました。
次は、状態が大きく変化した際の対応と、ご家族へのサポート体制についてご紹介します。
お別れが近づいたときの準備と支え
病状が進行し、タロくんの体力が目に見えて落ちてきた頃、ご家族には「お別れが近いかもしれない」という現実をお伝えする必要がありました。これは決して冷たく突き放すものではなく、“最期まで一緒に過ごすための心と環境の準備”をする大切な時間です。
痙攣発作に備えた準備
- 腫瘍からの炎症や毒素が神経に影響し、痙攣を引き起こす可能性を説明
- 発作時の動画や資料を共有し、実際にどう対応するかを事前に練習
- 発作止めの注射薬を準備し、使用手順をしっかり指導
予期せぬ急変に備えることは、ご家族の混乱を最小限にし、タロくんの苦痛を和らげる大きな支えとなります。
精神的な支えとしてのマインドセット
この時期は、ご家族の心の揺れもとても大きくなります。「これでよかったのか」「もう限界かもしれない」という葛藤が渦巻く中、私たちは“事実と感情を切り分ける”ことを意識的にお伝えします。
- 「苦しいのは誰か」を常に考える
- 客観的な指標(呼吸数、食欲、体温など)で状況を判断する
- 冷静な判断が“穏やかだった”という記憶につながる
家族で過ごす最後の時間の整え方
最期の時間を家族でどう過ごすか。その準備を一緒に進めていきました。
- リビングのソファーの下に寝床を設置し、家族全員の目が届く場所に
- タロくんの大好きだったおもちゃや毛布をそばに置く
- できるだけ一緒の時間を増やすために、仕事のスケジュールを調整
そして2025年3月18日、タロくんは玄関先から見える桜の木に花が咲き始めた頃、家族に見守られながら、自宅で穏やかに旅立ちました。
在宅緩和ケアがもたらした意義と学び
大型犬であるタロくんが腹腔内腫瘍を抱えながらも、自宅で穏やかに過ごし、家族に見守られて旅立つことができた背景には、在宅緩和ケアという選択の中で、日を追うごとに強まったご家族の覚悟があったからだと思っています。別れを受け入れることは決して単純なことでなければ簡単なことでもないです。
大型犬特有の在宅管理の難しさと工夫
- 移動が困難なため、通院による負担が非常に大きい
- 身体が大きいため、寝床の調整や介助が必要になる
- 酸素管理や点滴量の設定も、小型犬・猫とは違う基準が求められる
これらの課題に対し、私たちは個別にプランを設計し、無理のない範囲での皮下点滴、酸素環境の構築、家族全員が協力できる診療体制を整えました。
ご家族の心の成長と準備の重要性
診断直後は混乱していたご家族も、診療を重ねていくうちに表情が変わっていきました。必要な情報を伝え、段階的に心構えをしていくことで、タロくんの最期に「やれることはやれた」と感じられたそうです。
- 急変時に慌てないよう、シミュレーションを行った
- 苦しみを和らげる投薬のタイミングを練習
- お別れの時間を意識的に作るように指導
在宅緩和ケアは「医療」だけではない
点滴や投薬といった医療行為だけでなく、「最期をどこで迎えたいか」「誰と過ごしたいか」といった“生き方”に寄り添うケアこそが在宅緩和ケアの本質です。
タロくんが見せてくれた穏やかな最期と、ご家族が示してくれた愛情と覚悟は、これから同じような病と向き合う子たちへの大きなヒントになると確信しています。
◆-----------------------------------◆