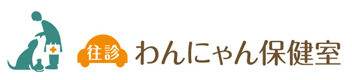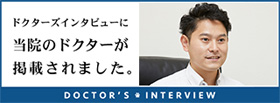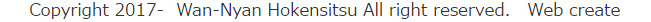犬の腎臓腫瘍は、比較的まれではありますが進行が早く、発見時にはすでに他の臓器へ転移していることも多い疾患です。外科的な摘出や抗がん剤治療といった選択肢がある一方で、高齢や他の持病、性格的な問題、通院によるストレスを理由に、在宅での緩和ケアを選ばれるご家族も増えてきました。
このブログでは、犬の腎臓腫瘍において在宅医療という選択がどういったものか、どのようなケアが可能なのかをご紹介していきます。在宅でもしっかりとしたサポートが可能であることを、少しでも多くのご家族に知っていただけたら嬉しいです。
目次
- 犬の腎臓腫瘍とは?〜発見されにくい沈黙の病〜
- 診断のきっかけと代表的な症状
- 治療の選択肢:外科手術、抗がん剤、そして在宅緩和ケア
- 在宅医療を選ぶ理由:通院負担とQOLへの配慮
- 在宅緩和ケアでできること
- 皮下点滴や内服薬:腎臓腫瘍に対する支持療法
- 症状の進行とご家族の心構え
- わんにゃん保健室の在宅ケア:犬とご家族に寄り添う選択
犬の腎臓腫瘍とは?〜発見されにくい沈黙の病〜
犬の腎臓腫瘍は発生頻度としては決して高くはありませんが、発見が遅れることが多く、発見されたときにはすでに進行しているケースも少なくありません。腎臓は沈黙の臓器とも言われ、腫瘍がかなり大きくなるまで明確な症状が出にくいのが特徴です。
腎臓に発生する腫瘍の種類
- 腎細胞癌:最も代表的な原発性腎腫瘍
- 腎リンパ腫:リンパ腫が腎臓に転移または原発する形
- 移行上皮癌:腎盂や尿管に関係する腫瘍
特に腎細胞癌は片側の腎臓に発生することが多く、外科手術によって摘出可能であることもありますが、発見されたときには肺や肝臓などへの転移が確認されていることもあります。
進行しても症状が出にくい理由
腎臓は二つある臓器であり、一方が障害されてももう一方が機能を補うことで、体の代謝が維持される場合が多いため、片側の腫瘍だけでは目立った症状が出ないまま進行してしまうことがあります。
在宅ケアを検討するケースとは
- 高齢で全身麻酔のリスクが高い
- すでに転移が認められており、根治が望めない
- 性格的に通院や入院が著しいストレスになる
こうした理由から、腎臓腫瘍の犬においては、在宅でできるだけ穏やかに過ごさせてあげたいと考え、緩和ケアを選択されるご家族も増えてきています。
診断のきっかけと代表的な症状
犬の腎臓腫瘍は進行するまで明確な症状が出ないことも多いですが、ある程度腫瘍が拡大したり、腎機能が落ちたり、または他の臓器に転移したことによる症状から発見されることがあります。
腎臓腫瘍でよく見られる症状
- 食欲不振や体重減少
- 元気の低下や動きの鈍さ
- 持続的な嘔吐
- 血尿や頻尿などの泌尿器症状
- 腹部の膨満感やしこりを触れる
検査で発見されるケースも
症状があまり出ていない場合でも、定期的な健康診断での血液検査や腹部超音波検査で偶発的に腫瘍が見つかることもあります。特に高齢犬では、腎機能マーカー(BUN、クレアチニンなど)の上昇が見られた際に画像検査を併用することで、腫瘍性病変が判明する場合もあります。
当院の往診(在宅緩和ケア)では、検査の時に検査項目を絞らずに決まった項目は必ず検査することをスクリーニング検査として実施しています。費用面では項目を絞った方がいいとされる考え方もありますが、結果として見落としがあった場合に、あの時検査していればと後悔しないためです。追加検査で再度採血などのストレスをかけるくらいであれば、1度の検査で、かつストレスが限定されている範囲で、得られる所見は集めることを推奨しています。
診断後の選択肢
- 外科手術による腎摘出(片側のみの場合)
- 抗がん剤治療(腫瘍の種類によっては適応あり)
- 積極的治療が難しい場合は在宅での緩和ケアの選択
ご家族の意向や年齢、性格、基礎疾患の有無を踏まえたうえで、治療方針を決めていく必要があります。
在宅ケアで注意したいこと
犬の腎臓腫瘍に対する在宅緩和ケアを行う際には、いくつかの重要なポイントに注意を払う必要があります。これらを適切に管理することで、愛犬が少しでも快適に過ごせるようサポートできます。
定期的な健康状態のモニタリング
- 毎日の食欲、飲水量、排尿・排便の状態を観察し、変化があれば記録する。
- 体重測定を定期的に行い、体重減少がないか確認する。
- 呼吸状態や粘膜の色(歯茎など)をチェックし、異常がないか観察する。
異常時の対応策の準備
- 急な体調不良や症状の悪化に備え、かかりつけの獣医師と連絡を取れる体制を整える。
- 緊急時に使用できる薬剤や処置方法について、事前に指導を受けておく。
- 夜間や休日でも対応可能な動物病院の連絡先を把握しておく。
犬猫も人と同じく、終末期に向かって歩んでいく道のりは、決して平坦ではないです。そのため、急変はつきものであり、その時にどうするのかという具体的なアクションプランを、ご家族で決めておきましょう。
ご家族の精神的・身体的負担の軽減
- 在宅ケアは決して楽ではなく、ご家族にも負担が大きいため、無理のない範囲で行うことが重要。
- 必要に応じて、訪問看護サービスやペットシッターなどの外部サポートを検討する。
- ご家族自身の休息やリフレッシュの時間を確保し、心身の健康を維持する。
在宅緩和ケアを行う際には、これらのポイントを踏まえ、愛犬とご家族双方のQOLを維持することが大切です。
在宅緩和ケアを選択するタイミング
腎臓腫瘍の犬において、在宅での緩和ケアを選ぶべきタイミングにはいくつかの目安があります。体調の変化や治療の限界を迎えたとき、ご家族と愛犬が一緒にいられる時間を大切にするための選択肢となります。
治療の限界が見えたとき
- 外科手術や化学療法などの根治治療が難しいと判断されたとき。
- 腫瘍の進行により、症状が再発・悪化し続けているとき。
- これ以上の積極的治療が犬にとって苦痛を伴うと判断されたとき。
通院や入院が犬にとって大きな負担になるとき
- 移動に伴うストレスや興奮で体調が悪化するリスクがある場合。
- 入院が長期化し、愛犬が精神的に不安定になっているとき。
- 通院後にぐったりする、食欲が落ちるなどの反応が見られる場合。
ご家族が「自宅で過ごさせたい」と感じたとき
- 最期は病院よりも住み慣れた自宅で迎えさせてあげたいと考えたとき。
- ご家族が在宅でのケアを希望し、覚悟を持って支えていく意志を持ったとき。
- 愛犬が家族のそばで安心して過ごす姿が望ましいと感じたとき。
在宅緩和ケアへの切り替えは、診断名や病期だけで判断するものではありません。犬の状態、ご家族の想いと覚悟、生活スタイルなど、すべてを総合的に考慮した上で決定することが大切です。
ここまでで、愛犬が腎臓腫瘍を抱えたことを知った後のことを書かせていただきました。
最後に、わんにゃん保健室が提供する在宅ケアのサポート体制についてご紹介します。
わんにゃん保健室の在宅ケアサポート体制
わんにゃん保健室では、腎臓腫瘍を含む終末期の疾患に対して、ご家族とペットが安心して在宅で過ごせるよう、きめ細やかなサポート体制を整えています。
初診時の丁寧なカウンセリング
- 初診では獣医師が訪問し、最大2時間かけて病歴やご家族の希望を丁寧にヒアリング。
- 動物看護師の同行は、必要に応じて検査や処置の際に対応。
- 在宅で可能な処置の範囲や、今後の経過予測についても具体的に説明。
緩和ケアプランの個別設計
- 診察や検査結果に基づき、症状のコントロールを目的とした投薬プランを作成。
- 皮下点滴や注射薬など、ご家族でも管理可能な方法をご提案。
- 酸素環境の構築や床の工夫など、生活環境の最適化も併せてアドバイス。
ご家族への細やかなフォローアップ
- 緊急時に備えた対応や頓服薬を準備。
- 状態が変化しやすい子には、必要に応じて週1回以上の定期訪問。
在宅ケアにおいて、最も大切なのは「この子の最期は、どこでどんな風に過ごさせてあげたいのか」という視点です。
病気と闘うのではなく、病気を受け入れ、共に穏やかな時間を生きていく。
わんにゃん保健室は、ご家族と愛犬、愛猫の最後の時間に寄り添った在宅緩和ケアを最後まで提供します。
◆-----------------------------------◆
――――――――――――
【執筆・監修】
江本宏平(在宅緩和ケア専門獣医師)
【病院名】
往診専門動物病院 わんにゃん保健室
【診療受付】
10:00~19:00(不定休)
【住所】
東京都台東区松が谷3-12-4 マスヤビル
【連絡先】
03-4500-8701(留守電対応)
Mail:house.call@asakusa12.com
※診療中につき電話をとることができないことが多いです。
往診をご希望の際には、問合せフォームからご連絡をいただくか、留守番電話にメッセージをお残しください。
【SNS】
Instagram:
@wannyan_hokenshitsu(診療紹介)
@koheiemoto(家族に向けた心のケア)
note:
https://note.com/koheiemoto
【ご挨拶】
末期がん、腎不全、心疾患など、 高齢の犬や猫に対する在宅緩和ケア・ターミナルケアを専門としています。
ご自宅でのケアに限界を感じたとき、 病院への通院が難しくなってきたとき、
「最後まで苦しませたくない」という気持ちに寄り添った診療を行っています。
【診療対応地域(往診対応エリア)】
東京都:
23区全域、国立市、府中市、三鷹市、稲城市、調布市、狛江市、武蔵野市
神奈川県:
川崎市(高津区・宮前区・川崎区)、横浜市(青葉区・港北区・神奈川区・鶴見区)
埼玉県:
戸田市、川口市、草加市、蕨市、八潮市、三郷市
千葉県:
松戸市、市川市、浦安市、習志野市