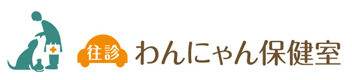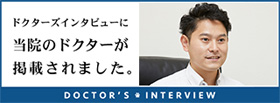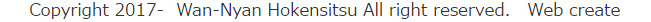1. 心臓血管肉腫とは(進行性の悪性腫瘍)
血管肉腫とは?(血管内皮由来の疾患)
心臓血管肉腫は、大型犬に多く見られる進行性の悪性腫瘍で、血管内皮細胞が腫瘍化することで発生します。この病気では、腫瘍の破裂や進行によって血液や液体が心臓周囲に漏れ出し、心タンポナーデと呼ばれる状態を引き起こすことがあります。
心タンポナーデとは、心臓とその周囲を覆う膜(心嚢膜)の間に液体が溜まり、心臓が正常に動けなくなる状態です。この結果、呼吸困難や失神、急な衰弱といった症状が現れ、適切な処置が必要となります。
心臓に発生する血管肉腫と心タンポナーデの影響
心臓血管肉腫は症状が進行するにつれて、次のような症状が見られることが多いです。
いつも元気な犬が散歩を嫌がる、疲れやすくなるなどの変化(運動量の低下)、安静時でも呼吸が浅く速くなる(呼吸が苦しそうになる)、歯茎が白っぽくなるなど、貧血の兆候(顔色の変化、可視粘膜蒼白など)、そして急な体調不良を起こし、突然立てなくなる、失神することもあります。
心タンポナーデを解除するためには、心嚢水抜去と呼ばれる処置が必要です。この処置では、心臓周囲に溜まった液体を針で抜くことで心臓の圧迫を緩和します。ただし、心嚢水抜去は、往診で対応できる往診専門動物病院は多くないかもしれません。当院では、鎮静処置を行なった上で実施していますが、大型犬の場合には比較的痛みにとても強い子が多いので、無処置で心嚢水抜去に耐えてくれることも多くあります。
外科手術や積極的な治療は難しい
心臓血管肉腫の治療では、外科手術や抗がん剤が選択肢として挙げられることがありますが、多くの場合、効果を期待するのが難しいとされています特に大型犬では、以下の理由から在宅緩和ケアへの移行が選ばれることが多いです。心臓血管肉腫は進行が早く、緩和ケアで穏やかな生活を目指す選択が重要視されます。特に大型犬では、動かすことがそもそも小型犬と比べて重さの観点から難しい場合が多く、動物病院への高頻度な通院に耐えられず、在宅緩和ケアへの移行を選ばれることが多いです。
大型犬は比較的内服薬を受け入れてくれるため、週1回程度の定期検査、状態のよって内服薬の用量や種類を変更するなど、これらはほとんどの往診専門動物病院で管理が可能だと思います。
大型犬の場合、歩行が難しくなった段階で往診を検討するのが良いタイミングだと思います。心臓血管肉腫では、症状が進むと週1回以上の検査や内服薬の調整が必要になるため、無理な通院を避けるためにも、早めの往診切り替えが推奨されます。
次のセクションでは、実際の症例を基にした在宅緩和ケアの経過について詳しくご紹介します。
2. 大型犬の心臓血管肉腫(ゴールデンレトリバー)
病気の発覚(呼吸困難と急な失調症状)
大型犬で心臓血管肉腫が見つかるきっかけは、急な体調変化が多い傾向にあります。例えば、次のような症状から病気が発覚することが一般的です。
①散歩中に急に立ち止まり、動けなくなる
②普段と違う浅い呼吸や疲れやすい様子が見られる
③食欲旺盛だった犬が食事中に戸惑うような行動を見せる
④失神や突然の衰弱
これらの症状が出現した場合、緊急で動物病院を受診すると、心嚢水の貯留が確認され、心タンポナーデを起こした可能性が多いです。心嚢水の貯留が進むと心臓が圧迫され、正常な血液循環が阻害されるため、迅速な対応(心嚢水抜去)が必要になります。
心嚢水抜去で一時的に安定を取り戻す
心嚢水が貯留している場合、心嚢水抜去という処置が行われます。この処置では、心嚢膜に針を刺して溜まった液体を抜くことで、心臓の動きを改善します。抜去後は、呼吸が楽になる、顔色が戻り元気を取り戻す、そして抜去後には食欲や行動が一時的に改善するなどが期待できます。
ただし、心嚢水の貯留は繰り返し起こることが多いため、1回の処置だけで完治するものではありません。症状が再発するたびに抜去を行う場合、頻繁な通院が必要になるため、大型犬では体力面の負担が大きくなります。
在宅緩和ケアへの切り替えとその背景
通院が難しくなる段階で、在宅緩和ケアを選択する飼い主様も多くいらっしゃいます。特に、大型犬では次の理由から在宅ケアが選ばれることが一般的です。
①体力の低下に伴う通院リスク
心嚢水や胸水が貯留し始めた段階では、頻繁な検査や内服薬の調整が必要になります。大型犬の場合、これらを通院で対応するのは犬と飼い主様双方にとって大きな負担です。体力的な負担の増大と時間的な拘束は、直接的に精神面の崩壊を招いてしまうかもしれない、ということを忘れないでくださいね。
②緊急時の対応準備
心嚢水の貯留が急激に悪化した場合、自宅での酸素環境整備や注射薬の準備が重要となります。内服薬が飲めなくなることを想定し、皮下点滴の準備も行うことで、緊急時の対応がスムーズになります。もちろん、寝たきりの大型犬を動物病院まで連れて行ける環境があるのであれば、おかしいと判断したらすぐに動物病院に連れて行きましょう。
③穏やかな最期を目指したケア
終末期では、苦痛を最小限に抑えたケアが重視されます。飼い主様と犬が安心して過ごせる環境を整えるため、在宅ケアが選ばれるケースが増えています。
大型犬の場合、比較的内服薬をしっかり受け入れてくれるため、症状が安定している間は薬でのコントロールが可能です。しかし、心嚢水や胸水が貯留し始めたら週1回以上の検査と内服薬の調整が必要になるため、早めに往診を利用し、飼い主様が適切にケアできる体制を整えることが推奨されます。
次のセクションでは、在宅緩和ケアで具体的にどのような対応が行われるかについて詳しくご紹介します。
3. 在宅緩和ケアの具体的な実施内容
初期対応とご自宅でのケアプラン
心臓血管肉腫を抱える大型犬にとって、在宅緩和ケアの最初のステップは症状の安定化と家の中でご家族様だけでできる在宅ケアプランの作成です。特に心嚢水や胸水が貯留し始めた場合、定期的な検査と緊急時の対応準備が不可欠です。
1. 酸素環境の整備
呼吸が苦しい場合、酸素濃度を高めた環境を整えることが重要です。在宅での酸素環境には、
酸素発生装置と酸素ボンベの適宜設置及び運用によって、犬の状況に合わせた酸素環境を構築していきます。
酸素発生装置は、基本的にはずっと酸素を供給できる装置であり、維持することを目的に使用していきます。地域によっては酸素ボンベの設置が可能な場合があります。
東京23区であれば、私たちの方から診療で必要だと判断した場合に処方箋を作成することで、ご自宅に酸素ボンベを設置することが可能です。
急激な呼吸状態の悪化時に即座に酸素を補給するための準備は欠かさないようにしましょう。また、大型犬の場合には、酸素ハウス内で管理することは、経験上行われないことが多いです。
大型犬が入り、なおかつ中で動きがとれるくらいの快適さを酸素ハウスに求めた場合、それだけの空間を酸素化することはかなり難しくなってきます。
ただ、ご希望があれば、私たちが酸素環境を構築させることは可能ですので、往診の時にご相談ください。
入らなかった場合には、直接吹きかけてあげることで、酸素供給を目指します。大型犬の場合、酸素を直接鼻先に吹きかける方法が現実問題として最も選ばれる手法だと思われます。
2. 内服薬と皮下点滴の準備
大型犬では、比較的内服薬をしっかり受け入れてくれるケースが多いです。
これを活かし、症状のコントロールには、症状に応じて利尿薬や心臓をサポートする薬を中心に据えつつ、急変で内服薬が飲めなくなった場合に備え、家の中での皮下点滴を導入しましょう。皮下点滴を準備しておくことで、幅広い医薬品の投与が可能になります。
急変時の対応方法
心嚢水や胸水が貯留し始めた場合、症状の急変が避けられないケースもあります。在宅ケアでは、急変時に飼い主様が適切に対応できるよう、事前の準備とアクションプランが重要です。
1. 心嚢水抜去の検討
心嚢水が急激に貯留した場合、速やかに心嚢水抜去を行う必要があります。
当院では、獣医師だけでなく愛玩動物看護師が同行し、保定を含む適切な対応を提供します。
鎮静後に心嚢水抜去を行いますが、大型犬では痛みにとても強い場合が多いため、無鎮静で実施できている印象を受けています。
当院以外の往診専門動物病院でも、状況次第では心嚢水抜去が可能なこともあると思いますが、抜去ができないために内服や注射薬で貯留した心嚢水が減少するかを見守るとされた場合には、別の往診専門動物病院を検討しましょう。
2. 家族ができるアクションプラン
飼い主様には、緊急時にどのように対応するべきかを具体的にお伝えしています。
呼吸が苦しい場合には、事前に準備された酸素運用を行い、まずは酸素の供給をサポートしてもらいます。
飲食ができなくなった場合には、内服薬を無理に飲ませるのではなく、皮下点滴や注射薬で対応することをお勧めします。
なお、もし動物病院まで連れて行けるのであれば、動物病院へ連れていくべきか、在宅で見守るべきかの判断基準を事前に話し合っていただきます。
終末期のサポート(ターミナルケア)
在宅緩和ケアの目的は、愛犬ができるだけ苦しまずに、家族と穏やかな時間を過ごせるよう支えることです。終末期(ターミナル期)では緩和ケア期と比べて、より具体的に別れを意識した取り組みをさせていただきます。
例えば呼吸状態の管理で、酸素を十分に嗅がせていても呼吸状態が悪化していく場合には、安定剤や鎮痛剤を適切に使用し、少しでも今という時間を楽に過ごしてもらうのかを考えていきます。
ただ、この先の数分後、数十分後に訪れるのは、お別れになると思います。それでも最後の苦しい時間を短くしてあげたいと考え、実施されるご家族様もいます。
最後の時間を、少しでも不安や苦しみが少ないように、家族の不安を軽減するためにも、状況に応じた具体的なアドバイスを行います。
在宅緩和ケアは、大型犬の体調や家族の状況に合わせて柔軟に対応できるケア方法です。
次のセクションでは、大型犬において通院が難しい理由と、往診を選ぶメリットについて詳しくご紹介します。
4. 呼吸が苦しい大型犬に往診を選ぶ理由
通院のリスクと体力消耗の危険性
大型犬にとっても、心臓血管肉腫の進行に伴う通院は、体力面・精神面で大きな負担となります。
特に呼吸が苦しい場合や心嚢水、胸水が貯留している場合、通院によるストレスが病状をさらに悪化させる可能性があります。
通院時のリスク
移動中の体力消耗がまずは大きいです。
持ち上げるにも、移動させるにも、胸郭の圧迫や興奮は避けなければいけません。
また、車の揺れも胸水貯留や心嚢水貯留を伴う犬猫には大きなストレスとして影響を与える可能性があります。次に待ち時間によるストレスです。
これは、毎回の積み重ねで、犬だけでなくご家族様の精神的な負担につながってきます。
ただし、心嚢水貯留をすでに起こしているわんちゃんが失神した場合などは別で、心嚢水抜去が可能な往診獣医師を待つことができなければ、動物病院に急ぐ連れていくことを検討しましょう。
往診専門動物病院でも酸素環境構築指示、心嚢水抜去、皮下点滴は可能
往診を利用することで、大型犬に必要なケアを自宅で受けられる環境を整えることができます。
特に次のようなケアは、往診の利点を活かして実施可能です。
1. 酸素供給の環境整備
自宅での酸素環境の構築により、通院せずに呼吸困難を緩和できます。酸素発生装置や酸素ボンベを利用した適切な運用方法を指導します。
2. 心嚢水や胸水の抜去
必要に応じて心嚢水や胸水の抜去を往診で実施します。これには鎮静処置が必要な場合があるので、事前に往診専門動物病院に確認しておきましょう。この時の保定には十分な知識と技術が必要なため、必ず動物看護師にお願いしましょう。
3. 内服薬や注射薬の調整
状態に応じた内服薬の調整を行い、犬が無理なく服用できる形でサポートします。心嚢水貯留が見られる犬猫では急変はつきものですので、急変時のために皮下点滴や注射薬を準備し、対応力を高めましょう。
在宅ケアの安心感
往診で行う在宅緩和ケアは、飼い主様と犬にとって多くの安心感を提供します。
1.犬の負担軽減
慣れ親しんだ自宅環境で診察やケアを受けることで、大型犬のストレスを最小限に抑えられます。
2.ご家族様の安心
大型犬を連れて通院する負担がないため、飼い主様が犬に集中してケアを続けられます。
3. 緊急時の対応力向上
酸素環境や注射薬の準備を事前に整えることで、急変時にも冷静に対応できます。
往診は大型犬の終末期ケア(ターミナルケア)に最適な選択肢
大型犬の心臓血管肉腫は、進行とともに通院が難しくなり、より頻繁なケアが求められる病気です。往診は、犬のストレスを最小限に抑えつつ、飼い主様が安心してケアを続けられる体制を提供します。
次のセクションでは、これらの取り組みがもたらす穏やかな最期と、在宅緩和ケアの重要性についてまとめてご紹介します。
5. まとめ:在宅緩和ケアがもたらす安心と穏やかな最期
呼吸状態の安定がもたらす生活の質(QOL)の向上
心臓血管肉腫の進行に伴い、大型犬は呼吸困難や体力の低下といった症状に苦しむことが多くなります。在宅緩和ケアでは、呼吸状態を安定させる環境を整えることで、犬が少しでも穏やかに過ごせる時間を増やすことが期待できます。
生活の質を高めるポイント
1. 酸素環境の整備により、呼吸が苦しい時間を減らせます。
2. 内服薬や皮下点滴を利用することで、症状をコントロールしつつ快適な生活を維持します。
3. 自宅でのケアが可能になることで、飼い主様と犬が安心して過ごせる環境を作ります。
大型犬の在宅ケアにおける往診の価値
特に大型犬では、通院による体力消耗やストレスが重篤な症状を悪化させる可能性があります。往診を利用することで、犬に必要なケアを自宅で受けられるだけでなく、飼い主様がケアに集中できる環境が整います。
往診が選ばれる理由
心嚢水や胸水が貯留し始めた際に必要となる週1回以上の検査や内服薬の調整を通院なしで実施できます。また、酸素供給や注射薬を事前に用意しておくことで、急変時にも柔軟に対応可能です。さらに、慣れ親しんだ自宅でケアを行うことで、犬がよりリラックスした状態で治療を受けられます。
大切な家族を見守る選択肢としての在宅ケア
在宅緩和ケアは、病気と闘うだけではなく、犬と家族が穏やかな時間を過ごすための選択肢でもあります。通院が難しい状態になったとしても、「何もできない」ということではありません。酸素供給や鎮痛剤の使用を通じて、犬の苦しみを軽減し、穏やかな最期を迎えるサポートが少しでもできるようにしておきましょう。最期の時間を自宅で過ごせることで、飼い主様と犬が特別な絆を再確認する機会になります。
在宅緩和ケアを検討されている方へ
大型犬の心臓血管肉腫や終末期ケアにおいて、往診による在宅緩和ケアは、犬と飼い主様にとって負担の少ない最適な選択肢です。病気の進行に伴い、通院が難しくなる前に往診を検討し、必要な準備を進めておくことで、安心してケアに取り組むことができます。
もし、呼吸状態の悪化や心嚢水の貯留などでお困りの際は、ぜひ一度、往診専門動物病院までご相談ください。愛犬の穏やかな時間を守るために、私たちは全力でサポートさせていただきます。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
愛犬の健康を守るための在宅ケアについて、少しでもお力になれる情報をお届けできていれば幸いです。
◆-----------------------------------◆
――――――――――――
【執筆・監修】
江本宏平(在宅緩和ケア専門獣医師)
【病院名】
往診専門動物病院 わんにゃん保健室
【診療受付】
10:00~19:00(不定休)
【住所】
東京都台東区松が谷3-12-4 マスヤビル
【連絡先】
03-4500-8701(留守電対応)
Mail:house.call@asakusa12.com
※診療中につき電話をとることができないことが多いです。
往診をご希望の際には、問合せフォームからご連絡をいただくか、留守番電話にメッセージをお残しください。
【SNS】
Instagram:
@wannyan_hokenshitsu(診療紹介)
@koheiemoto(家族に向けた心のケア)
note:
https://note.com/koheiemoto
【ご挨拶】
末期がん、腎不全、心疾患など、 高齢の犬や猫に対する在宅緩和ケア・ターミナルケアを専門としています。
ご自宅でのケアに限界を感じたとき、 病院への通院が難しくなってきたとき、
「最後まで苦しませたくない」という気持ちに寄り添った診療を行っています。
【診療対応地域(往診対応エリア)】
東京都:
23区全域、国立市、府中市、三鷹市、稲城市、調布市、狛江市、武蔵野市
神奈川県:
川崎市(高津区・宮前区・川崎区)、横浜市(青葉区・港北区・神奈川区・鶴見区)
埼玉県:
戸田市、川口市、草加市、蕨市、八潮市、三郷市
千葉県:
松戸市、市川市、浦安市、習志野市