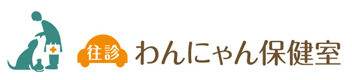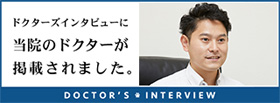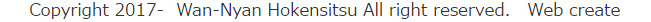1. 突然歩けなくなった大型犬で考えられる原因とは
大型犬が急に歩けなくなる原因で何が考えられるのか?
大型犬が急に歩けなくなる原因としては、神経系、筋骨格系、循環器系の問題が挙げられます。特に高齢の大型犬では、次のような疾患がよく見られます。
1. 椎間板ヘルニアや脊椎疾患
背骨に負担がかかり、神経が圧迫されることで、後肢が麻痺することがあります。これも結構多い印象で、早期であれば高用量のステロイドなどによる対応で改善することが望めますが、その重症度をまずは評価してあげたいことから、CT、MRIを撮ることができる施設への通院をお勧めします。
2. 関節炎や股関節形成不全
大型犬に多い疾患で、関節の炎症や変形によって痛みが生じ、歩行が困難になることがあります。股関節形成不全はゴールデンレトリバーでよく見る印象です。お尻を振るような歩き方(モンローウォーク)をしている大型犬と暮らしているのであれば、いつか必ず関節炎を発症して、歩きづらさが出てくるというのは覚えておいてあげましょう。急に歩けなくなるほどの関節炎や股関節形成不全は甘利見たことないですが、もしかしたら積み重ねで一気に痛みが出てしまった結果、立ち上がることを拒否してしまうのかもしれません。
3. 心臓病や血管の問題
心臓血管肉腫や心タンポナーデのように循環器系の疾患が進行すると、突然立てなくなる場合があります。大型犬で持病がなかったのに、急に失神を起こしてしまった場合には、心タンポナーデが発症している可能性があります。心嚢水が貯留してしまい発症するものですが、その原因で最も厄介なのが心臓血管肉腫です。心臓血管肉腫のゴールデンレトリバーの症例報告ブログをあげていますので、是非ご一読ください。
病気のサインを見逃さないために
歩けなくなる前に見られる小さなサインを見逃さないことが大切です。例えば散歩を嫌がるということがあります。急に散歩に行きたがらなくなるのは、痛みや体力の低下が原因かもしれません。次によろけたり、ふらついたりなど、転ぶことが増えることがあります。これは筋力低下や神経障害の兆候です。そのほかにも、もし心臓病が関与している場合であれば、呼吸が浅く速いなどの息苦しそうな様子が見られることがあります。これらのサインを早期に発見することで、適切な診療プランの決定が神族に行われ、その後の時間のQOL(生活の質)に大きく影響します。
気づいたときにすべき第一歩
大型犬が急に立てなくなった場合、慌てずに次のステップを踏むことが重要です。
1. 呼吸や意識の確認
息苦しそうな様子や意識がもうろうとしている場合は、直ちに動物病院に相談しましょう。 もしかするとそのまま入院管理になることもあるため、緊急で動物病院にいく場合には、入院になるかもしれないことを頭に入れておきましょう。
2. 歩行補助
移動が必要な場合は、抱き上げたりスリングを使って犬を安全に支えましょう。
3. 早めの診察
色々書きましたが、まずはかかりつけの動物病院に連絡して、最短でいつ診てもらえるのかを確認しましょう。もし移動が難しいと判断した場合には、往診専門動物病院に連絡します。東京23区内にお住まいの場合は、当院(わんにゃん保健室)が訪問できますが、すぐに対応できるかと聞かれると、往診という形態上、今すぐのお伺いは難しいことをご理解ください。待てるのかどうかはご家族の判断となりますが、大型犬で起立困難となると、往診を依頼することで、わんちゃんだけでなくご家族にとっても移動の負担を減らす選択肢になります。
突然の体調不良は飼い主様にとっても驚きと不安が伴いますが、冷静に対応することで、犬にとって最善のケアを行うことができます。
次のセクションでは、東京中央区で急に立ち上がれなくなってしまったゴールデンレトリバーの犬吉くんについてご紹介します。
急に立てなくなったゴールデンレトリバーの犬吉くん
散歩好きな大型犬が見せた突然の異変
犬吉くんは、東京中央区で暮らす明るく元気な大型犬でした。毎日の散歩を何より楽しみにしており、家族の誰よりも早起きして散歩の準備をするほどでした。ところが、ある日、散歩の途中で急に足を止め、そのまま動けなくなってしまいました。
飼い主様は最初、「疲れただけかな?」と思っていたそうですが、その後も歩きたがらない様子が続き、不安を感じて動物病院に連れて行きました。
動物病院での診断と心配な症状
動物病院での診察の結果、犬吉くんは心臓の病気と神経障害の可能性を指摘されました。さらに、血液検査とエコー検査で、心臓周囲に液体が溜まる心嚢水貯留が確認され、すぐに抜去処置が必要とされました。
心嚢水貯留が進んだ犬には顔色(歯茎の色)の変化(白っぽくなる、もしくは青白くなる)特に横になりたがらず、呼吸が浅く速くな理、座ったままでいることが多くなり、特に横になりたがない印象です。 好物に興味を示さなくな理、元気や食欲の低下が著しく起こります。
もしこれらの症状が現れた場合、直ちに医療対応が必要です。
ご家族の想いと在宅医療の選択
診断後、動物病院で心嚢水の抜去処置が行われましたが、病状が進行する可能性を考慮し、飼い主様は通院ではなく在宅医療に切り替える選択をしました。大型犬の場合、通院は体力的にも負担が大きく、呼吸が苦しい状況での移動は非常に危険です。
犬吉くんの飼い主様は、「少しでも穏やかな時間を家で過ごさせてあげたい」という想いから、往診専門の動物病院に相談し、在宅医療の準備を始めることにしました。
次のセクションでは、急な体調不良時にどのような初期対応が必要か、そして早めの診察がいかに重要かをご紹介します。
3. 初動の速さが重要
「急に立てなくなった」に対する初期対応
大型犬が急に歩けなくなったり立てなくなった場合、初期対応が犬の命を守るうえで非常に重要です。以下のポイントを押さえて、冷静に行動しましょう。
1. 状況と状態を冷静に観察
大前提として、緊急時ほど冷静になることを意識しましょう。いつからの症状なのか、兄をしているときにそれが起きたのか、そして呼吸状態はいかがでしょうか。呼吸が浅く速くなっているか、または苦しそうな様子がないか確認します。歯茎や舌の色を見て、蒼白や青白い場合は緊急性が高い可能性があります。
2. 安静を保つ
無理に動かそうとせず、静かで落ち着いた場所に犬を寝かせましょう。この時、過剰に触ったり、無理に歩かせようとしないように注意します。急いで動物病院に連れて行きたい気持ちは山々ですが、その時点で胸部を圧迫してしまうと、致命的な結果になってしまうかもしれないので、注意しましょう。
3. 動物病院への連絡
緊急で受診できる動物病院に連絡し、状況を伝えて指示を仰ぎます。東京中央区を含む23区内では、夜間救急に対応可能な病院も複数ありますが、全国になると地域ごとで夜間も診療してくれる獣医師もいれば、全くいないということもあると思います。もしものことすぎるため、事前に動物病院と連携をとっておくことも難しいと思いますので、ご家族がアクションプランを決めておきましょう。
動物病院での検査とその後の流れ
動物病院では、身体検査や炎症や貧血の有無を調べるための血液検査、心臓や関節、脊椎など、内部の状態を確認するためのX線検査や超音波検査(エコー検査)などの画像検査、心嚢水や胸水が貯留している場合には鎮静処置を伴った抜去処置が行われるのが一般的です。
初期対応で重要なのは、早期に適切な診断と治療を受けることです。特に心嚢水貯留が疑われる場合、早めの抜去が犬の体調を大きく改善させる可能性があります。
早めの在宅医療で生活の質を守る
診断後、通院でのケアが難しい場合は、早めに在宅医療(在宅緩和ケア)を検討することも大切です。在宅緩和ケアでは犬の体力を温存させるだけでなく、通院によるご家族の負担を回避できます。動や待ち時間が不要になることで、ケアに集中できます。そして、自宅での在宅ケアや介護のお話をさせていただき、ご家族のニーズに合わせた診療計画が立てられます。
在宅医療では、定期的な往診を通じて症状を管理し、急変時に備えた準備を進めることが可能です。早めに体制を整えることで、犬と飼い主様が穏やかな時間を過ごすサポートができます。
次のセクションでは、在宅医療を開始した犬吉くんの診療プランについて具体的にご紹介します。
4. 在宅医療の始まり(犬吉くんの診療プラン)
自宅でできるケアの準備(環境整備のポイント)
犬吉くんの在宅医療を開始するにあたり、まずは自宅での日常ケアと介護などの環境を整えることが重要でした。大型犬の場合、快適な環境を作るためには次のような点に注意が必要です。
1. 安静を保つスペースの確保
滑りにくいマットやカーペットを敷き、犬がリラックスして横になれる場所を準備します。部屋の温度や湿度も病態た状態によって適宜調整し、少しでも過ごしやすい環境へと進化させていきます。
2. 移動の補助器具の準備
ハーネスやスリングを用意し、立てなくなったときに安全に移動できるようにします。
3.必要な医療器具の配置
酸素発生装置や皮下点滴セットなど、緊急時に対応できる医療資材や機材をご自宅に設置していきます。今後起こりうる症状などに対し、その時ご家族が緊急通院以外を選択できるように、ご自宅の中に対策を残して行きます。
呼吸、食欲、排泄状態をモニタリングする方法
在宅医療では、犬の体調を日々観察することが欠かせません。以下のポイントを飼い主様に共有し、犬の健康状態を把握していただきました。
1. 呼吸状態のチェック
呼吸が浅く速い場合や、苦しそうにしている場合は、すぐに酸素を供給します。鼻や歯茎の色が蒼白または青白くなった場合も注意が必要です。
2. 食欲の観察
食べる量や食事への興味を毎日確認します。食欲がない場合は早めに報告いただきました。
3. 排泄の管理
排尿・排便の頻度や量、形状などを記録し、異常があれば診察時に伝えていただきます。
ご家族と連携した柔軟な診療プラン
犬吉くんの在宅医療では、ご家族との密な連携が診療プランの中心でした。次のような計画を立てて進めました。
1. 定期的な往診
最初のうちは1〜3日に1回の往診で経過観察と検診、医薬品投与による反応を評価していき、落ち着きを取り戻してきた頃からは、週1回程度の往診で、心嚢水や胸水の状態をチェックし、内服薬の調整を行いました。
2. 急変時の対応準備
在宅緩和ケアにおいて、症状の急激な悪化はつきものです。この時、回復を望む場合には緊急で動物病院に飛び込むことをお勧めします。しかし、移動中に苦しむこと、そして改善してもまた繰り返すのが、この緩和ケア期の後半〜ターミナルケア期です。もう通院は厳しいとした場合に何もできないという状況にならないように、酸素環境や注射薬の準備を整え、緊急時に備えた具体的な対応策を共有しました。
3. 家族と相談しながらのケア
犬吉くんの体調やご家族の希望に合わせて柔軟にケアプランを調整し、犬と家族が安心して過ごせる環境をサポートしました。
在宅医療を開始することで、犬吉くんは自宅で安心して穏やかな日々を過ごせるようになりました。次のセクションでは、急変時に必要なアクションプランと飼い主様ができる対応について詳しくご紹介します。
5. 緊急時のアクションプラン(家族がその時できること)
急変時に役立つ在宅緩和ケアの知識
大型犬の在宅医療では、症状が急変したときに家族がどのように対応するかが重要です。特に呼吸困難や突然の虚脱といった緊急事態に備えるため、事前に必要な知識と準備を整えておくことをおすすめします。以下のポイントを基に、犬吉くんの飼い主様にも対応をお伝えしました。
1. 犬の状態を冷静に観察する
呼吸が浅く速い、もしくは呼吸のリズムが乱れている場合は緊急対応が必要です。歯茎や舌の色が白っぽくなる、冷たくなるなどの変化をチェックします。
2. 慌てずに安静を保つ
急に動かしたり、無理に立たせようとせず、犬がリラックスできる体勢を維持します。
3. すぐに酸素供給を開始する
酸素発生装置を利用して呼吸をサポートします。大型犬の場合、鼻先に酸素を直接吹きかける方法が現実的です。
酸素供給や皮下点滴での対応準備
急変時には、酸素環境や注射薬を活用したケアが効果的です。酸素発生装置や酸素ボンベを設置し、使用方法を家族全員が理解しておくことで、急な呼吸状態の悪化に備えて酸素環境が整備されます。酸素を使い始めたら、犬の呼吸状態がどのように変化するかを観察し、獣医師に状況を共有しましょう。
そして、おそらくこの後からは内服薬が飲めないと思われます。内服薬が飲めなくなった場合に備え、皮下点滴で薬剤を投与できる体制を整えます。犬吉くんのお母さん、お父さんには、皮下点滴の方法を事前に練習していただきました。犬吉くんは何の不安もなさそうに皮下点滴を受けてくれ、まるで全部を理解しているような雰囲気でした。
緊急時に家族の誰が何をするのか役割を決めておくと、スムーズに対応できます。
動物病院へ連れていくべきか判断する基準
急変時、動物病院に連れていくか在宅で見守るかの判断は、症状や犬の状態によります。以下の基準を参考に、適切な選択を行いましょう:
この話からはズレてしまいますが、まだ治療中であり回復を望める場合には、通院という手段を消さないほうがいいです。ただ、もう厳しいと判断された以降は、もう通院をさせないで、家で看取ってあげる前提の上で判断をすることになると思います。酸素供給や皮下点滴を行っても呼吸状態が改善しない場合には、医薬品の内容変更や用量変更を行い、明らかに痛みを伴っている場合や苦しそうな鳴き声を出す場合には、痛み止めを追加使用するなど、在宅でできる緊急時の苦痛緩和用の医薬品は、ご自宅に事前準備することは可能です。
犬吉くんの飼い主様も、酸素供給や注射薬の準備を整えたことで、急変時にも落ち着いて対応できました。次のセクションでは、往診を活用した在宅医療の具体的な内容について詳しくご紹介します。
6. 在宅医療でできること(往診による柔軟なケア)
自宅での診療がもたらす犬の安心感
大型犬が通院する際の負担は非常に大きいため、自宅で診療を受けられる往診は、犬にとっても飼い主様にとっても安心できる選択肢です。犬吉くんのケースでも、次のようなメリットがありました。
1. 慣れた環境でストレスを軽減
犬吉くんは、自宅の落ち着いた環境で診療を受けることで、動物病院の通院後の疲れた表情がなく、きっと通院ストレスが緩和されたんだと思います。家の中での訪問診療中もリラックスした様子を見せてくれることが多く、診察がスムーズに進みました。
2. 体力温存に寄与
動物病院への通院だと、絶対に必要となる移動や待ち時間がなくなり、体力が温存されたような印象だと、ご家族から伺いました。往診であれば、呼吸が苦しい状態でも、移動の負担を感じることなく診療を受けることができました。
3. 飼い主様との一体感
家族が診療中もずっとそばにいてくれる安心感が、犬吉くんを精神的に支えてくれたからなのか、終始落ち着いて診察を受けてくれました。診療全体を通して、ご家族も安心した表情で診察に立ち会ってくれて、説明もわかりやすかったと話してくれました。
内服薬の調整と注射薬による症状コントロール
在宅医療では、犬の状態に応じた柔軟な治療プランが可能です。犬吉くんの場合は、症状に応じて利尿薬や心臓サポート薬を調整し、症状の進行を抑えました。大型犬は比較的内服薬を受け入れやすい傾向があり、犬吉くんも治療初期は内服薬で安定した生活を送ることができました。また、常に内服薬を飲めなくなった場合に備えておくことも欠かせません。犬吉くんでも同様に、内服薬が飲めなくなった場合に備え、皮下点滴による薬剤投与を準備しました。ご家族に点滴の方法を事前トレーニングを持って覚えていただき、急変時にも対応可能な体制を整えました。そして、呼吸困難が見られる場合には、酸素供給を組み合わせたケアを実施しました。また、痛みが強い場合には、どこをどう判断することで痛みなのかどうかが判断できるとお伝えし、痛みを確認した場合に使用できるように、鎮痛剤を準備させていただき、苦痛を和らげました。
定期的な往診で見守る大型犬の生活
犬吉くんの場合、週に1回の定期往診を実施し、状態の確認と治療プランの見直しを行いました。往診のたびに次の点を評価しました:
1. 呼吸状態の確認
心嚢水や胸水の貯留の有無を超音波検査で確認し、必要に応じて抜去を実施しました。
2. 生活の質(QOL)
1週間を通じての食欲や排泄の状況を把握し、日常生活の質を維持するためのアドバイスを行いました。
3. ご家族のマインド
家族の不安や質問に丁寧に対応し、一緒に治療プランを調整しました。プラン構築の上で最も重要なことは、ご家族の心を把握することです。何をどんな風に悩んでいるのかを常に意識しながら状況説明を行うと、意外な言葉にご家族の反応が見えることがあり、その場合には別角度から同じような説明をしたりなどで、マインド把握を図ります。
往診による在宅医療は、犬の状態に応じた柔軟なケアを可能にし、飼い主様と犬が安心して穏やかな時間を過ごせる環境を提供します。次のセクションでは、犬吉くんが在宅医療でどのように穏やかな日々を過ごしたのか、その最期の時間についてご紹介します。
7. 犬吉くんの穏やかな道のり
ご家族との時間を大切にした在宅ケアの取り組み
在宅医療が始まってからの犬吉くんは、自宅という安心できる環境で、家族と特別な時間を過ごしました。通院の負担がなくなり、食欲が少しだけ回復したことで「らしさ」を取り戻してくれました。犬吉くんは、在宅医療の開始後にお気に入りのフードを再び楽しむようになりました。心嚢水抜去による呼吸の改善や内服薬の調整により、体調が安定し、今まで通りの家族時間が戻ってきたようだとお話しされていました。大型犬の心臓血管肉腫に伴う急な症状は、心嚢水の抜去が完了すると、次の瞬間からいつも通りの元気さが戻ってくることが多いです。もちろん、いきなり元気に走り回るかというと違いますが、起き上がれなかったのが家の中を普通に歩けるくらいまで回復し、ご飯だって食べてくれるようになります。
「もう一度散歩を」の願いが叶った日
抜去した日の昼過ぎに、家族の支えのもと、短い散歩に出ることができました。ゆっくりとしたペースでしたが、大好きな近所の公園で風を感じることができたその日は、家族全員にとって忘れられない思い出となったそうです。
本来であれば、ぐったりするたびに動物病院に連れて行かなければいけなかったのが、往診と出会うことができて以来、通院の必要なく、すべてが家の中で行えていました。
自宅で過ごす時間は、犬吉くんにとっても家族にとっても、かけがえのないものです。家族が交代でそばに座り、撫でたり話しかけたりする中で、犬吉くんはリラックスして眠る姿を見せてくれました。
最期を自宅で迎えることがもたらす安心感
犬吉くんの最期の時間は、家族全員に見守られながら、本当に穏やかで静かなものでした。心タンポナーデが進行する中でも、酸素供給による呼吸のサポートや安定剤の使用により、犬吉くんが苦しまずに過ごせていました。苦痛は最小限に抑えることで、治療ではない緩和ケアによって、緩やかな最後を描いてくれました。
家族との深い時間と後悔のないお見送り準備
家族全員が犬吉くんを囲み、話しかけたり、好きだったおもちゃやタオルをそばに置いたりして、犬吉くんにとって安心感のある時間を作りました。最期の瞬間は少し苦しそうでしたが、家族に見守られながら旅立つことができました。
病状の進行や予想される変化について事前に共有していたことで、ご家族は心の準備を整え、最後の呼吸が始まった時も、犬吉くんに寄り添い続けることができました。見送った後も、「自宅で一緒に過ごす選択ができて良かった」という思いを語ってくださいました。
穏やかに過ごすための心の準備
在宅医療では、犬の体調管理だけでなく、家族が心穏やかに愛犬を見送るためのサポートも重要です。犬吉くんのケースでは、次のような取り組みを行いました。
1. 病状の進行についての丁寧な説明
ご家族が、今自分の子がどんなん状態で、今後何が起こりうるのかを知っておくことが重要です。心嚢水が再び貯留した際の兆候や、最期が近づくと見られる変化について具体的にお伝えしました。症状の一つひとつをご家族と共有することで、ご家族が抱える漠然とした不安の軽減を図りました。
2.最期の時間の過ごし方の提案
ご飯を食べられなくなった時は強制給餌をするのか、食べないことで餓死してしまうのでは、いつまで皮下点滴を打つのか、打たないほうが枯れるように亡くなるとどこかのブログでみた、など多岐にわたる質問を受けるのが、私たちが専門的に取り組んでいる在宅緩和ケア、そしてターミナルケアです。医療面のことはもちろん、できるだけわかりやすい言葉でシンプルにお伝えすることで、「わからない不安」を減らして行きます。また、「声をかけ続ける」「触れてあげる」など、犬が安心できる接し方をアドバイスしました。家族ができることに集中できる環境を整えることで、心の準備を後押ししました。
犬吉くんの在宅医療の取り組みは、家族と犬が互いに支え合いながら、特別な時間を過ごすことを可能にしました。次のセクションでは、当院の往診を紹介させていただきます。東京23区での訪問による在宅緩和ケアを検討されているご家族は、まずは当院がどのようなサポートを提供しているのかをご覧いただける内容となっています。
8. 東京23区での在宅医療なら往診専門動物病院わんにゃん保健室へ
東京23区を中心に近隣地域までの広範囲対応
当院では、東京23区を中心に、近隣地区まで在宅医療を提供しています。特に大型犬のように移動が困難な場合、往診は犬の体力や飼い主様の負担を軽減する最適な選択肢です。
1. 東京23区全域をカバーした往診専門動物病院
多くの往診専門動物病院が、地域を限定しての訪問としており、地区を越えてまでの往診を定期的に提供できるところは希少です。私たちは、中央区、江東区、品川区などの都心部から足立区や葛飾区といったエリアまで対応しています。また、診療時間も飼い主様の生活スタイルに合わせた時間帯にできるだけ柔軟に対応しています。
2. 酸素環境や医療機器の導入サポート
酸素環境にここまで力を入れている動物病院は、出会ったことがないですが、最後の時間に酸素発生装置があることはかなり便利です。どんな環境で管理するかによって、酸素発生装置1台ではなく2台にするか、または酸素ボンベがあったほうがいいか、などを考えています。もし呼吸を苦しがっているような症状があれば、ご家族から直接レンタルできる酸素発生装置よりも、処方箋を出さないと入手できないもののほうが、実際に使ってみて使いや水です。
当院では、酸素環境を整えたいご家族の場合に、在宅での使用方法を丁寧に説明し、急変時にも対応できるようサポートさせていただいています。
大型犬も安心の在宅医療サービス
大型犬は、小型犬に比べて通院の負担が大きく、特に歩行が難しくなった段階での往診が強く推奨されます。当院では、大型犬の在宅医療において次のようなサービスを提供しています。
1. 心嚢水や胸水の抜去はご自宅で可能
状況に応じて、自宅で心嚢水や胸水の抜去を実施し、呼吸の負担を軽減します。保定業務は経験豊富な愛玩動物看護師が行うため、飼い主様が負担する必要はなく、わんちゃんへの負担も最小限に抑えます。
2. 診察中の呼吸悪化に対する対応準備
胸水貯留や心嚢水貯留などの症例では、処置時のストレスで呼吸状態が容易に悪化します。そのため、保定には十分に注意を払うのはもちろんのこと、呼吸状態悪化を回避するために、常に酸素ボンベを携帯しています。酸素供給を迅速に行える環境下で処置することで、通常の往診に比べて安心して対応できる環境を提供します。
3. 内服薬や注射薬による症状コントロール
こちらも通常の動物病院と比べると差はほとんどないのですが、往診専門動物病院と比較すると、当院は複数の内服薬を保持しています。その分柔軟に医薬品変更の対応が可能であり、わんちゃんの状態に合わせて、注射薬変更も可能という柔軟な処方対応を行います。 内服薬が飲めなくなった場合でも、注射薬であれば皮下点滴に混ぜることで投与が可能です。
飼い主様に寄り添う柔軟な診療プラン
当院では、ご家族の不安を軽減し、わんちゃんもご家族も穏やかに過ごせる環境を提供することを目指しています。
1. 十分な時間枠による安心空間での診察
診療空間は家の中であり、実際の生活環境の中に改善点があればアドバイスをさせていたいています。診療時間枠も、通常の動物病院での診療では難しい時間枠にて、しっかりと診察させていただきます。初診では1時間半〜2時間半ほど、再診でも30分〜1時間ほどと、予約枠は状況次第で変動しますが、ゆっくりと十分な時間を取ることを大切にしています。
定期訪問の頻度やケア内容を都度調整し、飼い主様と一緒に最適な方法を探ります。
2. 在宅医療の経験豊富なスタッフ
獣医師と動物看護師がチームとなり連携を密に取り合うことで、全症例を全員で診ていきます。医療面だけでなく、日常ケアや介護、食事などの悩みも、すべて把握させtいただいております。生活環境を見させていただくことで、どこに不安を感じているのか、どんな悩みがありそうか、など、獣医師、動物看護師の観点から見つめられるのも強みです。
飼い主様との密なコミュニケーションを大切にし、不安や疑問に丁寧にお答えすることで、質の高いケアを提供します。
3. 穏やかな最期を迎えるためのサポート
わんちゃんとご家族が最後まで安心して過ごせるよう、緩和ケアからターミナルケアまで一貫してサポートします。最期の時間をご家族と共に穏やかに過ごせるよう、心の準備やケア方法をお伝えします。
お気軽にお問い合わせください
大型犬の在宅医療に関してお困りの際は、ぜひ当院までご相談ください。東京以外でも対応可能ですので、移動の負担を減らしたい、愛犬が最後まで安心して暮らせる環境を構築してあげたい、治療ができなくても苦痛だけは緩和してあげたい、など、診療にて全力でサポートさせていただきます。まずはお電話または問い合わせフォームから、現在の状況をお聞かせください。
わんちゃんだけでなく、その横で必死に向き合ってくれているご家族にとっても、残された時間を少しでも穏やかに過ごしていただけるよう、最善のケアについて一緒に考えていきましょう。
◆-----------------------------------◆
――――――――――――
【執筆・監修】
江本宏平(在宅緩和ケア専門獣医師)
【病院名】
往診専門動物病院 わんにゃん保健室
【診療受付】
10:00~19:00(不定休)
【住所】
東京都台東区松が谷3-12-4 マスヤビル
【連絡先】
03-4500-8701(留守電対応)
Mail:house.call@asakusa12.com
※診療中につき電話をとることができないことが多いです。
往診をご希望の際には、問合せフォームからご連絡をいただくか、留守番電話にメッセージをお残しください。
【SNS】
Instagram:
@wannyan_hokenshitsu(診療紹介)
@koheiemoto(家族に向けた心のケア)
note:
https://note.com/koheiemoto
【ご挨拶】
末期がん、腎不全、心疾患など、 高齢の犬や猫に対する在宅緩和ケア・ターミナルケアを専門としています。
ご自宅でのケアに限界を感じたとき、 病院への通院が難しくなってきたとき、
「最後まで苦しませたくない」という気持ちに寄り添った診療を行っています。
【診療対応地域(往診対応エリア)】
東京都:
23区全域、国立市、府中市、三鷹市、稲城市、調布市、狛江市、武蔵野市
神奈川県:
川崎市(高津区・宮前区・川崎区)、横浜市(青葉区・港北区・神奈川区・鶴見区)
埼玉県:
戸田市、川口市、草加市、蕨市、八潮市、三郷市
千葉県:
松戸市、市川市、浦安市、習志野市