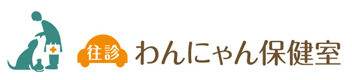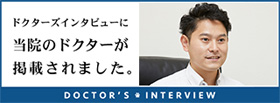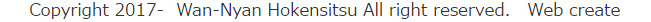「最近よく吐くようになった」「やせてきた気がする」「水をよく飲むようになった」----そんな猫ちゃんの変化に気づいた飼い主さんへ。
それは、もしかすると慢性腎不全(CKD)のサインかもしれません。
慢性腎不全は、特に中高齢の猫に多く見られる、ゆっくりと進行していく病気です。はっきりとした症状が出にくいため、「ただの老化かな」と見過ごされることも少なくありません。
しかし、実は"気づいたときにはかなり進行していた"ということが多いのです。
診断を受けたばかりの飼い主さんにとって、「治療すれば治るのか」「何をすればいいのか」「点滴や薬は必要なのか」と、不安がたくさんあるのではないでしょうか。中には、「通院が難しいけれど、ちゃんとケアしてあげたい」と悩まれている方もいるかもしれません。
このブログでは、そんな飼い主さんに向けて、
- 慢性腎不全の症状や仕組み
- 病気の進行と治療の考え方
- ご自宅でのケアや点滴のこと
- 緩和ケアを取り入れるタイミングや意味
などについて、わかりやすくお伝えします。
"治療"だけではなく、"その子らしく穏やかに過ごすためのケア"という選択肢があること。
そして、それをご自宅でも実践できるという安心感を、ぜひ知っていただけたらと思います。
目次
- ≫ 第1章|症状から気づく猫の慢性腎不全
- ≫ 第2章|そもそも「腎不全」ってどんな病気?
- ≫ 第3章|「治療」と「ケア」のちがいを知っていますか?
- ≫ 第4章|慢性腎不全におけるステージと経過
- ≫ 第5章|おうちでできるケアと皮下点滴
- ≫ 第6章|点滴をやめるときの考え方と注意点
- ≫ 第7章|終末期ケアとしての緩和ケアのすすめ
- ≫ 第8章|"その子らしく"生きる時間を大切にする
- ≫ まとめ|腎不全の猫と向き合うために大切なこと
第1章|症状から気づく猫の慢性腎不全

慢性腎不全は、ゆっくりと進行する病気です。
初期の段階では目立った症状が現れにくいため、「なんとなく調子が悪そう」「ちょっと元気がないかな?」といった、ささいな変化がサインになることもあります。
ここでは、飼い主さんが気づきやすい症状を中心に紹介します。
食欲の低下や体重の減少
「最近、あまりごはんを食べなくなった」「前より体がほっそりしてきた」----そんな変化がある場合、
腎臓の機能が低下し、老廃物が体に溜まってきている可能性があります。
特に、ウェットフードや好物にも反応が鈍いときは、消化器症状や吐き気が背景にあることも。
慢性腎不全の初期〜中期に見られることが多いサインです。
水をよく飲む、尿の量が増える(多飲多尿)
「お水を飲む量が増えた」「トイレの回数やおしっこの量が多くなった」----これは、
腎臓がうまく尿を濃縮できなくなっているサインです。
体が水分を維持できなくなっているため、代わりにたくさん水を飲むようになります。
この症状は比較的わかりやすく、飼い主さんが最初に異変に気づくきっかけになることも多いです。
口臭、吐き気、元気の低下
進行とともに、体に老廃物がたまってくると、尿毒症という状態になることがあります。
これにより、
- アンモニアのような口臭
- 吐き気や嘔吐
- だるそうに寝てばかりいる
- 鳴かなくなった・反応が鈍い
などの症状が現れます。
こうした状態になると、見た目にも「具合が悪そう」と感じられることが増え、受診される方も多いです。
大切なのは「なんとなく変だな」と思ったら受診を
腎不全は、血液検査や尿検査によって初めてわかることがほとんどです。
「このくらい大丈夫かな」「年のせいかも」と思わずに、気になる変化があれば早めに獣医師に相談することが、
早期発見につながります。
第2章|そもそも「腎不全」ってどんな病気?

「腎不全」と聞くと、どこか重い響きがあるかもしれません。
実際、猫にとって腎不全は命に関わる病気ですが、その一方で、
上手にコントロールしながら生活していくこともできる慢性疾患です。
ここでは、腎不全の仕組みや、なぜ猫に多いのか、
という基本的な部分をやさしく解説します。
腎臓のはたらきと役割
腎臓は、血液をろ過して体内の老廃物を尿として排出したり、水分や電解質のバランスを保ったりする、
体の「フィルター」のような役割を果たす臓器です。
また、血圧の調整や赤血球をつくるホルモンの分泌など、実は多くの重要な働きを担っています。
腎不全になるとどうなる?
腎臓の機能が徐々に低下していくと、以下のようなことが起こります:
- 老廃物が体内にたまる(=尿毒症)
- 尿が薄くなり、体が脱水状態になりやすくなる
- 食欲が落ち、嘔吐や口内炎、貧血などが出てくる
こうした変化が少しずつ進行していくのが、**慢性腎不全(CKD)**です。
なぜ猫に多いの?
猫はもともと水をあまり飲まない動物であり、腎臓に負担がかかりやすい体のつくりをしています。
また、高齢になると腎臓の細胞が自然と減少していくため、加齢による腎機能低下が非常に多く見られます。
そのため、7歳を過ぎた頃から定期的な検査をすることで、早期発見・早期ケアにつながることが多いのです。
第3章|「治療」と「ケア」のちがいを知っていますか?

猫の慢性腎不全は、「治すこと」よりも「付き合っていくこと」が大切な病気です。
けれど、診断を受けたばかりの飼い主さんの多くが「治療をすれば治る」と思ってしまうのも自然なこと。
ここでは、"治療"と"ケア"の違いについて、あらためて整理してみましょう。
「治療」は病気を治すためのアプローチ
多くの病気では、薬や手術などを用いて病気の原因を取り除き、元の健康な状態に戻すことを目指します。
これがいわゆる「治療」であり、完治がゴールです。
しかし慢性腎不全の場合、すでに失われた腎臓の機能は、残念ながら元に戻すことはできません。
「ケア」は"その子らしく過ごす"ためのサポート
慢性疾患において重要なのが、「症状をコントロールしながら、できるだけ快適に暮らす」という視点です。
これが「ケア」や「緩和ケア」の考え方です。
- 吐き気や食欲不振をやわらげる
- 脱水や貧血を防ぐ
- 無理のないペースで生活できるようにする
こうした日々の積み重ねが、その子の生活の質(QOL)を保つことにつながります。
緩和ケアは"最後の選択肢"ではありません
「緩和ケア」と聞くと、「もうなにもできないときに行うもの」と思われがちですが、それは大きな誤解です。
実際には、腎不全と診断されたそのときから、ケアの視点はすでに必要なのです。
往診などでおうちの環境に合わせたケアを行うことで、通院が難しい子でも安心して過ごせますし、
飼い主さんの心の負担も軽くなります。
第4章|慢性腎不全におけるステージと経過

猫の慢性腎不全は、進行の程度によって大きく4つのステージに分類されます(IRISステージ分類)。それぞれのステージによって、現れる症状や必要なケアが異なります。
飼い主さんが「いまどの段階なのか」を知ることは、今後の治療・ケアの方針を立てるうえでとても大切です。
ステージ1・2:気づきにくい初期段階
初期の段階では、血液検査でやや異常値が出るものの、見た目には大きな症状が出ないことが多いです。
この時期には、
- 多飲多尿
- 軽度の体重減少
- 少し元気がない
といったささいなサインが見られることも。
この段階でフードの見直しや水分補給など、早めのケアを始めることで、
その後の進行を緩やかにすることが期待できます。
ステージ3:症状が明らかになってくる
この頃になると、
- 吐き気や嘔吐
- 食欲のムラ
- 明らかな体重減少
- 口臭や口内炎
などが見られるようになります。
脱水を防ぐための皮下点滴や、吐き気止め、胃薬の投与などが必要になることも増えてきます。
症状の出方や進行スピードには個体差があるため、獣医師との連携を密にしながら、
その子に合ったケアを行っていく時期です。
ステージ4(末期):QOLを重視するケアへ
血液検査の値が大きく悪化し、尿毒症の症状が顕著になってくるステージです。
この時期には、
- 毎日の皮下点滴や注射での薬剤投与
- ごはんが食べられない時のサポート
- 呼吸や循環のケア
などが必要になることも。
この段階では、症状を無理に抑え込むのではなく、いかに苦痛を軽減し、
穏やかな時間を保てるかがテーマになってきます。
第5章|おうちでできるケアと皮下点滴

通院が難しい子や、病院が苦手な猫ちゃんにとって、ご自宅でのケアはとても重要です。
なかでも「皮下点滴(皮下補液)」は、慢性腎不全の猫にとって代表的なケアのひとつです。
ここでは、おうちで行えるケアの選択肢と、皮下点滴について基本的なことを整理してみましょう。
皮下点滴の目的と効果
皮下点滴には、以下のような目的があります:
- 脱水を予防し、腎臓への負担を軽減する
- 老廃物を薄めて排出しやすくする
- 電解質のバランスを整える
- 食欲や元気の改善をサポートする
とくに自力で十分な水分が摂れなくなってきた子には有効で、症状の緩和に大きく貢献します。
点滴の頻度・量は、その子によりけり
皮下点滴の量や頻度は、腎不全のステージや体調によって変わります。
- 初期〜中期:週に2〜3回程度が目安
- 中~後期:1日おき、または毎日行うことも
ただし、点滴の"やりすぎ"も逆効果になる場合があり、浮腫や呼吸状態の悪化につながることも。
そのため、定期的な診察や血液検査を通じて、こまめに調整することが大切です。
ご家族でできる他のケア
皮下点滴のほかにも、おうちでできるケアには以下のようなものがあります:
- 食事:腎臓に配慮した療法食や、水分の多いウェットタイプを活用
- 投薬サポート:飲ませるのが難しい場合は注射薬への切り替えも相談
- 環境調整:静かで安心できるスペースの確保、トイレの位置の工夫
「無理をさせず、その子ができるだけ心地よく過ごせるように」を基本に考えていきましょう。
第6章|点滴をやめるときの考え方と注意点

「点滴を続けるのがつらそうだけど、やめていいのか分からない」
「点滴をやめる=見捨てることになってしまうのでは...?」
慢性腎不全のケアのなかで、**点滴の"やめどき"**に悩むご家族はとても多いです。ここでは、やめるタイミングの考え方と注意点を整理していきましょう。
点滴=延命治療とは限らない
点滴は、あくまでも水分補給や症状緩和の手段のひとつであって、
必ずしも「命を長らえさせるための延命措置」ではありません。
そのため、「点滴をやめる=諦める」ではなく、
"その子がつらくないように過ごす"ことを優先する選択として、やめる判断がなされることもあるのです。
やめる判断の目安とは?
点滴を中止するかどうかは、以下のような状態を見ながら検討していきます。
- ☑︎ 呼吸が苦しそう(過剰な水分が肺や胸にたまっている可能性)
- ☑︎ 点滴をすると具合が悪化する
- ☑︎ 尿がほとんど出なくなっている
- ☑︎ 点滴そのものが強いストレスになっている
獣医師の診察を受けながら、無理なく続けられるかどうかを見極めることが大切です。
やめる前にできる「調整」もある
いきなりやめるのではなく、以下のように段階的に減らしていく方法もあります。
- ☑︎ 回数を減らす(毎日→2日に1回、週3回 など)
- ☑︎ 量を減らす(1回100ml → 50mlなど)
- ☑︎ 内容を見直す(薬剤の追加や除去)
また、点滴の代わりに注射薬だけを使って症状を緩和する方法もあります。
獣医師と相談しながら、その子にとってのベストな選択肢を見つけましょう。
第7章|終末期ケアとしての緩和ケアのすすめ

「もう治せないなら、どうしてあげるのがいいのだろう...」
そんな問いに直面するのが、腎不全の猫ちゃんの"終末期"です。
この時期に大切なのは、無理な治療を続けるのではなく、穏やかに過ごせる時間を大切にすること。
それを叶えるのが、「緩和ケア(パリアティブケア)」という選択肢です。
緩和ケアとは、「苦しみを和らげる」ケア
緩和ケアとは、延命や治癒を目的とせず、つらい症状をやわらげてQOL(生活の質)を保つケアのことです。
たとえば:
- ☑︎ 吐き気や痛みを抑えるお薬(飲み薬または注射)
- ☑︎ こまめな体調チェック
- ☑︎ 食べられないときのサポート(流動食・補助食品 など)
「その子らしく」「穏やかに」「ご家族と一緒に」過ごす時間を守るための、優しいケアです。
「在宅でできる緩和ケア」という選択
往診による緩和ケアであれば、病院に通うストレスを避けながら、必要な処置や投薬を受けることができます。
実際に在宅で行われるケアの例:
- ☑︎ 注射薬の皮下投与(吐き気止め・痛み止めなど)
- ☑︎ 呼吸の苦しさを軽減する環境調整
- ☑︎ 看取りの相談や準備のサポート
「動物病院で最期を迎えたくない」「できるだけ家でそばにいてあげたい」
そんなご家族の気持ちに寄り添うのが、在宅緩和ケアの強みです。
ご家族の「後悔の少ない看取り」を支えるために
終末期のケアでは、「あのとき、こうしていれば...」という後悔がつきものです。
だからこそ私たちは、"医学的な正しさ"だけではなく、"
ご家族の気持ち"にも寄り添いながら選択していくことを大切にしています。
- ☑︎ 本当に必要な処置なのか
- ☑︎ その子が苦しくないか
- ☑︎ ご家族にとって納得のいく選択か
こうした問いを一緒に考えていけるのが、緩和ケアの本質です。
第8章|"その子らしく"生きる時間を大切にする

治療やケアの選択肢をひとつひとつ決めていくとき、
大切にしてほしい視点があります。
それは、「この子が"その子らしく"いられるか?」という問いです。
最後まで食べる楽しみを持てるように
たとえ少量でも、「好きなものを食べる」「自分で食べられる」という体験は、
猫にとってもご家族にとっても、その子らしさを保つ大きな要素です。
- ☑︎ 食べられるものを探してみる(好物・温めたごはん など)
- ☑︎ 自分で食べられないときは、そっとサポート
- ☑︎ 「食べない=もうダメ」と決めつけない
「一口でも食べてくれた」その瞬間が、宝物のような時間になることもあります。
無理のない範囲で、好きな場所・好きな空気の中で
通院や処置でぐったりしてしまうより、
家でゆったりと陽だまりにいるだけで、猫は穏やかで安心した表情を見せることもあります。
- ☑︎ ベッドの高さやトイレの位置を調整
- ☑︎ クッションや毛布であたたかい場所を作る
- ☑︎ お気に入りの場所にそっと連れて行く
「治す」ことだけが目的ではなく、今その子が快適でいられることに目を向けてみてください。
ご家族にとっても、心に残る時間を
「なにをしてあげればいいのかわからない」
そう思うこともあるかもしれません。
でも、ただそばにいるだけで、猫ちゃんにとってはかけがえのない時間になっています。
- ☑︎ 声をかけてあげる
- ☑︎ そっと撫でてあげる
- ☑︎ 一緒にいる時間を静かに過ごす
"最期までその子らしく"。
そして"最期までその子と一緒に"。
そんな時間が、ご家族にとっての癒しや後悔の少ない見送りへとつながっていきます。
まとめ|腎不全の猫と向き合うために大切なこと

猫の慢性腎不全は、ゆっくりと進行しながら、生活にさまざまな変化をもたらす病気です。
「治す」ことを目指すのではなく、**その子の体調や性格に合わせて"症状をやわらげながら支える"**という視点がとても大切です。
見逃したくないサイン
- 食欲低下、体重減少、嘔吐や口臭、多飲多尿などの初期症状
- これらを早めに気づくことで、暮らしの質を保ちやすくなります
点滴や投薬は"合う方法"で
- 自宅での皮下点滴、注射薬、飲み薬など、その子に合う形を選ぶ
- 点滴は無理に続けるものではなく、やめどきも見極めながら
緩和ケアは"腎不全と診断されたときから"始まっている
- 治すのではなく、できるだけつらくないように寄り添うケア
- 通院に頼らず、在宅でも十分にできるケアがある
最後まで"その子らしく"を大切に
- 食べる・眠る・安心する...そんな小さなことが、大きな癒しに
- ご家族が無理をせず、できる範囲で関わることが大切
慢性腎不全は、決して「絶望的な病気」ではありません。
早期からのケア、的確な判断、そして愛情ある寄り添いによって、猫ちゃんはとても穏やかに過ごすことができます。
少しでも不安を感じたときは、ひとりで悩まずご相談ください。
あなたと、あなたの大切な猫ちゃんのために、できるサポートを全力でさせていただきます。
――――――――――――
【執筆・監修】
江本宏平(在宅緩和ケア専門獣医師)
【病院名】
往診専門動物病院 わんにゃん保健室
【診療受付】
10:00~19:00(不定休)
【住所】
東京都台東区松が谷3-12-4 マスヤビル
【連絡先】
03-4500-8701(留守電対応)
Mail:house.call@asakusa12.com
※診療中につき電話をとることができないことが多いです。
往診をご希望の際には、問合せフォームからご連絡をいただくか、留守番電話にメッセージをお残しください。
【SNS】
Instagram:
@wannyan_hokenshitsu(診療紹介)
@koheiemoto(家族に向けた心のケア)
note:
https://note.com/koheiemoto
【ご挨拶】
末期がん、腎不全、心疾患など、 高齢の犬や猫に対する在宅緩和ケア・ターミナルケアを専門としています。
ご自宅でのケアに限界を感じたとき、 病院への通院が難しくなってきたとき、
「最後まで苦しませたくない」という気持ちに寄り添った診療を行っています。
【診療対応地域(往診対応エリア)】
東京都:
23区全域、国立市、府中市、三鷹市、稲城市、調布市、狛江市、武蔵野市
神奈川県:
川崎市(高津区・宮前区・川崎区)、横浜市(青葉区・港北区・神奈川区・鶴見区)
埼玉県:
戸田市、川口市、草加市、蕨市、八潮市、三郷市
千葉県:
松戸市、市川市、浦安市、習志野市