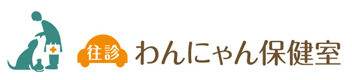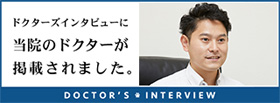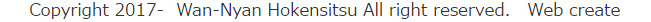ペットの病気が進行し、治療ではなく「今を穏やかに過ごすこと」を選ぶとき、ご家族は多くの不安や葛藤を抱えます。特に、猫の心筋症は進行性の病気であり、呼吸困難や胸水貯留といった症状が現れることがあり、通院そのものが負担になるケースも少なくありません。
この記事では、実際に心筋症を抱えた12歳の猫ちゃんが通院から在宅緩和ケアに切り替えた経緯を追いながら、具体的なケア内容や、在宅で得られる安心感についてお話しします。
ペットの「今」に寄り添う在宅緩和ケアは、治すことを目的とする医療とは異なり、ペットとご家族が一緒に穏やかな時間を過ごすための選択肢です。この記事が、同じように悩むご家族にとって少しでも参考になれば幸いです。
1. 心筋症の発覚と通院から在宅緩和ケアへの切り替え
12歳の健康診断で、猫ちゃんに心筋症が発覚しました。超音波検査と血液検査の結果、心臓に負担がかかりやすい状態であることが分かり、かかりつけの動物病院から「中央生存期間は3年程度」との説明を受けました。その日から、ご家族はできる限りのケアを始めました。心筋症を管理するための内服薬やサプリメント、食事管理がスタートし、当初は3ヶ月に1回の定期検査を行っていました。
最初の頃、猫ちゃんは通院にも慣れていて、特に問題なく動物病院に通えていました。しかし、心臓の数値が少しずつ悪化し、1ヶ月に1回の検査が必要になった頃から、通院後の疲れが目立つようになりました。キャリーケースに入れられると緊張し、帰宅後はぐったりして食欲が落ちることもありました。この状況を見たご家族は、通院による負担が猫ちゃんの状態を悪化させるリスクになると感じ始めました。
通院のたびに疲れ果てた姿を見るのは、ご家族にとっても辛いものでした。「もっと穏やかに過ごさせてあげられる方法はないか」という思いから、在宅緩和ケアへの切り替えを検討するようになりました。
在宅緩和ケアでは、通院のストレスがない状態で診療を受けられるため、猫ちゃんにとってもご家族にとっても大きな安心感があります。私たちの訪問診療では、まず初回の診察で猫ちゃんの状態を丁寧に確認し、ご家族と相談しながら、必要なケアを段階的に進めていくプランを立てました。
2. 在宅緩和ケア開始後の生活と診療
通院から在宅緩和ケアに切り替えた猫ちゃんは、自宅で穏やかに過ごせる時間が増えました。慣れた環境での診療は、猫ちゃんにとってストレスが少なく、ご家族にとっても安心できるものでした。
最初の診療では、全身状態を確認するための超音波検査を行いました。負担を最小限にすることを重視し、診療時間を短く設定しつつ、必要なデータをしっかりと収集しました。その後の診療でも、心臓の状態や呼吸の安定性を定期的に評価し、そのデータに基づいて内服薬やサプリメントの処方を調整しました。
内服薬の管理は、猫ちゃんの性格や状態に合わせてプランを組むことが重要です。ご家族の協力もあり、初期段階ではご飯に混ぜる方法で無理なく投薬を続けることができました。しかし、心臓の数値が悪化し始めた頃、呼吸状態の不安定さが目立つようになり、内服薬が負担となる可能性が高まったため、皮下点滴による薬の投与を開始しました。呼吸が苦しい猫ちゃんに無理に薬を飲ませることは逆効果となる場合もあるため、猫ちゃんの状態に合わせた柔軟なケアが求められます。
在宅緩和ケアでは、猫ちゃんが少しでも快適に過ごせる環境を整えることが重要です。私たちは、ご家族と相談しながら、自宅でのケア方法について細かくアドバイスを行いました。例えば、猫ちゃんがリラックスできる場所を確保し、静かで温度や湿度が適切な環境を作ることがポイントです。また、ご家族の希望や不安にも耳を傾けながら、日々のケアが無理なく続けられるようにサポートしました。
3. 胸水貯留の始まりと初期対応
在宅緩和ケアを始めてから半年後、猫ちゃんの呼吸状態に明らかな変化が見られました。呼吸が浅く速くなる頻呼吸や、お腹を大きく動かす努力呼吸の症状が目立ち始め、胸水貯留が疑われました。診察の結果、心筋症の進行による胸水貯留が確認され、早急に対応が必要な状況でした。
胸水が溜まると肺が圧迫され、酸素が十分に取り込めなくなるため、猫ちゃんにとって呼吸が非常に苦しくなります。この状況を緩和するため、初回の診療で胸水抜去を行いました。細い針を胸に刺して胸水を排出するこの処置は、猫ちゃんにとって負担がかかるため、慎重に鎮静と鎮痛を行いながら進めました。このとき、約50mlの胸水を抜去することができ、処置後は呼吸状態が大きく改善しました。
胸水抜去を行った後、呼吸の安定を維持するため、酸素環境の構築が必要になりました。酸素発生装置を設置し、猫ちゃんの状態に応じて酸素濃度を調整できる環境を整えました。酸素発生装置を導入することで、猫ちゃんが自宅で快適に呼吸を続けられるようになり、緊急時にも安心して対応できる体制が整いました。
胸水貯留は、心筋症が進行すると繰り返し発生することがあります。そのため、初回の胸水抜去後も定期的に診療を行い、胸水の量をチェックしながらケアプランを調整しました。2週間に1回だった胸水抜去の頻度は、猫ちゃんの状態が変化するにつれて徐々に増え、最終的には2~3日に1回の処置が必要となりました。
4. 酸素環境の構築と胸水貯留進行中のケア
胸水貯留が始まると、呼吸を楽にするための酸素環境が欠かせませんでした。私たちは、猫ちゃんの状態を見ながら酸素発生装置を導入し、細やかに運用方法を調整しました。
酸素環境を整える際には、酸素発生装置を設置するだけでなく、猫ちゃんが快適に過ごせる場所を確保することが重要です。最初はリビングの一角に酸素ハウスを設置し、出入り自由にして猫ちゃん自身が入りやすい環境を作りました。呼吸がさらに苦しくなった段階では、酸素濃度を高めた密閉型の酸素室での管理に切り替えました。
酸素発生装置の運用では、ご家族にも使い方を丁寧に説明しました。例えば、日中は酸素濃度を一定に保ちながら吹きかけで対応し、夜間は酸素ハウス内で管理する方法を採用しました。酸素濃度のモニタリングも行い、猫ちゃんの呼吸状態が安定する範囲を常に確認しながら運用を続けました。
胸水貯留が進行する中、頻繁な胸水抜去が必要となる一方で、体力を消耗させないよう配慮したケアも重要でした。胸水抜去の頻度が2~3日に1回に増えた頃には、処置を無理なく続けられるように以下のような工夫をしました。
1. 診療の際に必ず事前の鎮静と鎮痛を行うことで、猫ちゃんのストレスを最小限に抑える
2. 胸水抜去後の休息時間を確保し、体力の回復を優先する
3. 内服薬から皮下点滴への切り替えを進め、呼吸状態が悪化している猫ちゃんに負担をかけないよう調整
ご家族の協力を得ながら、猫ちゃんが少しでも穏やかに過ごせる環境を維持しました。酸素環境と適切なケアによって、呼吸の安定が保たれた時間が多く、猫ちゃんも安心した様子を見せてくれることが増えました。
5. ターミナルケアへの移行と最期の時間
胸水抜去の頻度が増え、2日に1回のペースになった頃、ご家族と相談しながらターミナルケアへの移行を進めました。この時期は、猫ちゃんにとってもご家族にとっても、大切な時間を穏やかに過ごすための準備期間でした。
胸水が抜去した翌日には再び貯留が見られることが増えたため、頻繁な処置が猫ちゃんの体力を奪う可能性があると判断しました。そこで、ご家族と相談の上、酸素環境をさらに強化し、胸水抜去の間隔を少し広げる形を取りました。酸素濃度を調整しながら、猫ちゃんが楽に過ごせるよう配慮を続けました。
ターミナルケアにおいて最も重要だったのは、猫ちゃんとご家族が心穏やかに時間を共有することでした。
1. ご家族と猫ちゃんがリラックスして過ごせる空間を整えるため、酸素ハウスの位置をリビングの中心に設置し、常に目が届くようにしました。
2. 呼吸が苦しくなる兆候が見られた際には、すぐに酸素濃度を上げるようご家族にお伝えし、適切に対応していただけるよう準備を整えました。
3. 猫ちゃんが快適に過ごせるよう、必要に応じて鎮痛剤や安定剤を使用し、痛みや不安を最小限に抑えるよう努めました。
最期の1週間は、猫ちゃんが自力で食事を取るのが難しくなりましたが、強制給餌は行わずに様子を見てあげることとしました。この時期、ご家族は「どんな選択が猫ちゃんにとって最善なのか」と悩む時間が多かったようです。しかし、最終的には「無理に処置を増やすのではなく、穏やかに過ごしてほしい」というご家族の希望に寄り添う形でケアを進めました。
2024年12月27日、ご家族全員が見守る中、猫ちゃんは静かに眠りにつきました。最期の時間は呼吸も安定しており、苦しむ様子は見られませんでした。ご家族がそばで声をかけながら撫でていたことで、猫ちゃんも安心感に包まれていたように感じます。
6. 在宅緩和ケアがもたらした安心と心の変化
在宅緩和ケアを選んだことで、ご家族と猫ちゃんにとって大きな変化がありました。それは「通院という負担から解放され、自宅で安心して過ごせるようになったこと」です。
猫ちゃんが通院していた頃は、キャリーケースに入れるたびに緊張し、帰宅後にはぐったりと疲れてしまう姿を見るのが辛いとご家族はおっしゃっていました。しかし、在宅緩和ケアを始めてからは、慣れた環境で診療を受けることができ、猫ちゃん自身も穏やかに過ごせるようになりました。
ご家族は「自宅で診療を受けられるという選択肢があることを知り、もっと早く相談すればよかった」と振り返っています。また、獣医師と直接相談しながら、猫ちゃんの状態に合わせた柔軟なケアプランを立てることで、「これでいいんだ」という安心感を持ってケアに向き合えるようになりました。
呼吸が苦しくなることが多かった猫ちゃんですが、酸素発生装置を導入したことで、日常的な安心感が大きく向上しました。酸素環境を整えることで呼吸が安定し、「いつでも適切なケアができる」という自信が、ご家族の心の負担を軽くしてくれたようです。
最期の時間を穏やかに迎えることができたのも、在宅緩和ケアのおかげと感じています、とご家族はおっしゃっていました。猫ちゃんが苦しむことなく静かに旅立つ姿を見届けることができ、ご家族も心を込めて最期の時間を見守ることができたことに安堵の表情を浮かべていました。
在宅緩和ケアは、ペットだけでなくご家族にとっても大きな安心感をもたらします。
7. わんにゃん保健室の在宅緩和ケア
わんにゃん保健室では、東京23区を中心に往診専門の在宅緩和ケアを提供しています。ペットが自宅で穏やかに過ごせるように、ご家族の不安や悩みに寄り添いながら、心のこもったケアを行っています。
在宅緩和ケアは、通院が難しくなったペットや、緩和ケアを希望するご家族にとって、大きな助けとなる選択肢です。当院では、以下の特徴的なサービスを提供しています。
1. ご家族に寄り添った柔軟なケアプラン
ペットの体調やご家族の希望に合わせて、個別のケアプランを作成します。内服薬や注射薬、皮下点滴などの医薬品管理を含め、最適な方法で対応します。
2. 酸素環境の構築と運用サポート
呼吸困難を抱えるペットのために、酸素発生装置や酸素ボンベの導入をサポートします。使用方法の説明や状態に合わせた調整も丁寧に行います。
3. 愛玩動物看護師とのチーム診療
獣医師だけでなく、愛玩動物看護師が同行することで、診療のサポートや保定などを適切に行い、ペットの負担を最小限に抑えます。
4. 緊急時の相談と事前準備
急変時に備えたアクションプランを事前にご家族と共有します。特にターミナル期では、急な呼吸困難や食欲低下などに適切に対応できるよう、薬の準備や酸素運用を含めたサポートを行います。
診療区域は東京23区全域をカバーしており、ペットの体調や緊急性に応じて迅速に訪問します。また、千葉、神奈川、埼玉の近隣地区までであれば、ご家族が少しでも安心してペットと過ごせるよう日程調整の上で訪問し、最善を尽くします。
在宅緩和ケアについてお困りのことがあれば、まずはご相談ください。通院が難しい状態や、ペットの体調に不安がある場合、事前の相談を通じて最適なケアプランを一緒に考えさせていただきます。
在宅緩和ケアやターミナルケアをご検討中のご家族様は、ぜひ一度わんにゃん保健室へお問い合わせください。
◆-----------------------------------◆
――――――――――――
【執筆・監修】
江本宏平(在宅緩和ケア専門獣医師)
【病院名】
往診専門動物病院 わんにゃん保健室
【診療受付】
10:00~19:00(不定休)
【住所】
東京都台東区松が谷3-12-4 マスヤビル
【連絡先】
03-4500-8701(留守電対応)
Mail:house.call@asakusa12.com
※診療中につき電話をとることができないことが多いです。
往診をご希望の際には、問合せフォームからご連絡をいただくか、留守番電話にメッセージをお残しください。
【SNS】
Instagram:
@wannyan_hokenshitsu(診療紹介)
@koheiemoto(家族に向けた心のケア)
note:
https://note.com/koheiemoto
【ご挨拶】
末期がん、腎不全、心疾患など、 高齢の犬や猫に対する在宅緩和ケア・ターミナルケアを専門としています。
ご自宅でのケアに限界を感じたとき、 病院への通院が難しくなってきたとき、
「最後まで苦しませたくない」という気持ちに寄り添った診療を行っています。
【診療対応地域(往診対応エリア)】
東京都:
23区全域、国立市、府中市、三鷹市、稲城市、調布市、狛江市、武蔵野市
神奈川県:
川崎市(高津区・宮前区・川崎区)、横浜市(青葉区・港北区・神奈川区・鶴見区)
埼玉県:
戸田市、川口市、草加市、蕨市、八潮市、三郷市
千葉県:
松戸市、市川市、浦安市、習志野市