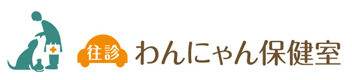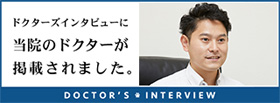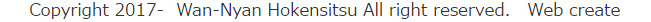東京都足立区に住む高齢のご夫婦と17歳の日本猫マルちゃん。幼い頃に保護されて以来、マルちゃんはずっとご夫婦と一緒に穏やかな日々を過ごしてきました。警戒心が強く、人見知りなマルちゃんにとって、ご家族以外の人と接することは難しく、通院も避けてきたため、健康管理はご家族が注意深く見守ることで行われていました。
2022年10月、食欲の低下と多飲多尿の症状から往診のご相談をいただき、診療の結果、慢性腎臓病ステージ4と診断されました。進行性の腎不全であることから、ご家族は在宅での緩和ケアを選択。病気と向き合いながらも、マルちゃんが最後まで穏やかに過ごせるよう、ご家族と私たちが一緒に支えていくこととなりました。
この記事では、マルちゃんが迎えた在宅緩和ケアの日々から最期までの様子を振り返りながら、ペットの緩和ケアがもたらす安心感とその重要性についてお伝えします。
1. 診断から始まった在宅ケア:マルちゃんとご家族の決断
2022年10月25日、マルちゃんにとって初めての往診が行われました。それまで通院を避けていたご家族にとっても、往診は初めての経験でしたが、ホームページやインスタグラムを通じて当院を知り、「これなら安心できそう」という思いからご連絡をいただきました。
マルちゃんは、ここ数ヶ月で水を飲む量が増え、多飲多尿の症状が見られていました。しかし、警戒心が強く、家族以外の人にはなかなか心を許さない性格だったため、通院という選択肢は考えられなかったとのことです。
腎臓病ステージ4の診断
往診時の診察と血液検査の結果、慢性腎臓病ステージ4と診断されました。脱水症状もあり、削痩が進行している状態で、ご家族には「これからは、穏やかに過ごせる緩和ケアを中心に考えていきましょう」とお伝えしました。
診断を受けたご家族は、「何もしてあげられなかったのでは...」と自分を責めるような言葉を口にされました。しかし、「これまで一緒に過ごしてきた日々が何よりの愛情です」とお話しすると、ご家族も少しずつ緩和ケアの大切さを受け入れてくださるようになりました。
往診による緩和ケアのスタート
ご家族の希望はただ一つ、「マルちゃんが安心して穏やかな時間を過ごせること」。この気持ちに寄り添い、月に1回程度の往診を行いながら、まずは内服薬を調整して腎臓の負担を減らすことを目指しました。
ご家族の不安を和らげるために、マルちゃんの状態やケアの方針を丁寧に説明し、「自宅でのケアが思った以上に簡単だ」と感じてもらえるようサポートしました。
2. 初期ケア:内服薬と定期的な往診
マルちゃんの在宅緩和ケアは、内服薬を中心とした初期ケアから始まりました。ご家族の不安を軽減しながら、マルちゃんが負担を感じないようなケアを目指しました。
飲みやすさを最優先した内服薬の調整
腎臓病ステージ4のマルちゃんにとって、内服薬は腎臓の機能を少しでも補助し、体調を安定させるために欠かせないものでした。しかし、警戒心が強く人見知りのマルちゃんにとって、投薬は一筋縄ではいきません。
そこで、ご家族の負担を減らすために、投薬の工夫を徹底しました。飲みづらい薬はすべて外し、飲ませやすい薬だけを選択。また、投薬用のおやつやカボチャを利用し、マルちゃんが自ら薬を受け入れられる方法を見つけました。これにより、スムーズに薬を飲ませることができ、ご家族も「こんなに簡単なら続けられそう」と安心されていました。
月1回の往診での定期チェック
最初の頃は月1回の往診で、マルちゃんの状態を確認しました。血液検査を通じて、腎臓の数値や脱水の程度を把握し、薬の種類や量を調整。削痩の進行や脱水症状を見ながら、ご家族にケアのアドバイスを行いました。
この段階では、マルちゃんはまだ自力で食べたりトイレに行ったりすることができたため、特別な介助は必要ありませんでした。しかし、次第に腎臓の数値が悪化し、食欲の低下や疲れやすさが目立つようになっていきました。
ご家族と共に進めたケア
腎臓病が進行する中、ご家族は「無理をさせずにできる範囲で頑張りたい」との意向を示されました。月1回の往診では、マルちゃんの状態だけでなく、ご家族の気持ちにも寄り添いながら、ケアの方法を相談し続けました。
3. 皮下点滴の導入:緩和ケアの本格化
マルちゃんの腎臓病が進行し、腎機能の低下が顕著になった頃、BUN(血中尿素窒素)の数値が80を超えるようになりました。この段階から、在宅での皮下点滴を導入することとなりました。ご家族の手による皮下点滴のケアは、緩和ケアの大きな一歩となりました。
BUNが80を超えたタイミングで皮下点滴を開始
腎臓病の進行に伴い、体内に老廃物が蓄積し、脱水が進むことでマルちゃんの体調も徐々に悪化していきました。特にBUNが急激な上昇を見せた頃からは、腎臓の負担を軽減するための水分補給が重要になります。
皮下点滴は、体に必要な水分を直接補う方法で、脱水を改善し、老廃物の排出を助ける効果があります。この時点で点滴は2日に1回の頻度で実施することになりました。
ご家族への皮下点滴トレーニング
マルちゃんの性格やご家族の環境を考慮し、お母さんが一人で点滴を行えるよう、トレーニングを行いました。
-
ポイント1:安心感の提供
初回は往診時に一緒に練習し、「これなら私にもできそう」と思っていただけるよう丁寧に指導しました。 -
ポイント2:マルちゃんの負担を軽減
点滴時にマルちゃんが緊張しないよう、普段リラックスして過ごしている窓際のベッドで実施。事前に温めた輸液を使用することで、冷たさによるストレスを軽減しました。 -
ポイント3:実用的なアドバイス
点滴中にマルちゃんが動いてしまわないよう、声かけや撫でるタイミングなど細かいアドバイスを行いました。
お母さんの努力と優しい手つきのおかげで、マルちゃんも点滴に慣れ、ご家族によるケアがスムーズに進められるようになりました。
皮下点滴による体調の安定
皮下点滴を導入したことで、マルちゃんの体調は一時的に安定しました。脱水が改善されたことで食欲が回復し、トイレにも自力で行ける日が増えました。ご家族も「点滴をすることで、マルが楽そうにしているのがわかる」と話し、日々のケアへのモチベーションがさらに高まりました。
4. 食欲の変化と寄り添うケア
腎臓病が進行すると、食欲不振は避けられない症状のひとつです。マルちゃんも徐々に食事の量が減り始めましたが、ご家族は「少しでも好きなものを食べさせてあげたい」と工夫を重ね、最期まで穏やかに過ごせるように努められました。
食欲が落ちたときの工夫
マルちゃんはもともと食事にこだわりが強い猫ちゃんでした。食欲が落ち始めた頃、ご家族はマルちゃんの好みを思い出し、特別なメニューを用意しました。
- カボチャを柔らかく煮て、少量をペースト状にしたもの
- 好物のウェットフードを少し温めて香りを引き立てたもの
これらの工夫により、マルちゃんは少量ずつでも食べてくれる日が続きました。「食べてくれるだけでホッとします」とご家族は嬉しそうに話していました。
最期の特別なご褒美:金目鯛の刺身
腎臓病の最期の段階では、猫が食べたがるものを優先することが大切です。マルちゃんも最期の1週間はほとんど食事を取らなくなりましたが、最終日の朝、ご家族が特別に用意した金目鯛の刺身を2切れも食べてくれました。
「最後にこんなに食べてくれるなんて」とお母さんは驚きと喜びで涙を浮かべていました。振り返って「今思えばエンジェルタイムだったのかもしれない」と話されていましたが、このエピソードはご家族にとってかけがえのない思い出となりました。
食事以外の穏やかな時間
食欲が完全に落ちてからも、マルちゃんは窓際のベッドで穏やかに過ごしていました。ご家族は湯たんぽで体を温めながら、そっと寄り添い、撫でたり声をかけたりしてマルちゃんが安心できるように努められました。
5. 最期の1週間:酸素室と窓際のベッドで穏やかに
マルちゃんが最期の1週間を迎える頃、腎臓病の進行により体力が大きく低下していました。動くことも少なくなり、ほとんどの時間を窓際のベッドで過ごしていました。それでも、ご家族はできる限りのケアを続け、穏やかで快適な時間を作ることに集中されていました。
呼吸状態の悪化と酸素室の準備
最期の1週間、呼吸が浅く荒くなってきたため、酸素室を準備しました。酸素発生装置を1台使用し、酸素濃度を保てる環境を整えましたが、マルちゃんは酸素室には入ろうとせず、窓際のベッドにいることを選びました。
ご家族は「マルちゃんが好きな場所で過ごせるのが一番」と考え、窓際の環境を快適に整えました。湯たんぽで体を温めたり、呼吸が楽になるよう酸素を直接ベッドの近くで吹きかけたりと、細やかな配慮を続けました。
トイレへのサポートと床環境の工夫
マルちゃんは最後の1週間も、トイレに行く努力を見せてくれました。自力で歩くことは難しくなっていましたが、少しでも自分でトイレに行きたいという意思を感じたご家族は、マルちゃんが安全に移動できるように床環境を整えました。
- 滑り止めマットを敷いて足元が滑らないようにする
- トイレの周囲にはペットシーツを敷き、失敗しても問題がないようにする
また、途中で倒れてしまうことも想定し、床にはクッション性のある素材を敷き詰め、マルちゃんが怪我をしないように配慮しました。「自分で歩いていこうとする姿が愛おしかった」とご家族は振り返ります。
ご家族の優しさに包まれた時間
最期の1週間、マルちゃんは食べることもほとんどなくなり、静かにベッドで横たわっていました。それでもご家族は、マルちゃんに寄り添い、撫でたり声をかけたりして、安心できる時間を作り続けました。
6. マルちゃんの旅立ちとご家族の思い
2024年6月3日、マルちゃんは窓際のベッドで、穏やかにその一生を閉じました。最期の瞬間まで、ご家族はマルちゃんに寄り添い、愛情に包まれた時間を過ごされました。
最後の朝
マルちゃんの最期の日、これまで1週間以上何も食べられなかったにもかかわらず、ご家族が特別に用意した金目鯛の刺身を2切れも食べてくれました。
「こんなにおいしそうに食べてくれるなんて、本当に嬉しかった」とお母さんは涙ぐみながら話されました。その姿は、ご家族にとって希望の光となり、最後の特別な思い出として心に残ったそうです。
最期の時
その日の午後、マルちゃんの呼吸は少しずつ浅くなり、窓際のベッドで静かに横たわっていました。ご家族はマルちゃんを抱きしめ、「ありがとう」「ずっと一緒にいられて幸せだったよ」と優しく語りかけていました。
そして、静かな時間が流れる中で、マルちゃんは最期の瞬間を迎えました。大好きなご家族に包まれながら、安らかな表情で旅立っていったのです。
ご家族から頂いた温かい声
ご家族は「マルちゃんが最期まで安心できる環境を整えてあげられてよかった」と話しておられました。「わんにゃん保健室さんにお願いして本当によかったです。最期の時間を穏やかに過ごせたのは、緩和ケアのおかげです」と感謝の言葉をいただきました。
看取りは悲しみと向き合う時間でもありますが、ご家族はマルちゃんと過ごした日々の温かさを胸に、少しずつ心を癒されていったようでした。
7. 在宅緩和ケアがもたらす安心感
在宅緩和ケアは、ペットとご家族が最後まで一緒に穏やかに過ごすための大切な選択肢です。マルちゃんとご家族のケースからも、その意義と効果が実感されました。
1. ペットが安心できる環境でケアを受けられる
通院が難しい猫ちゃんや、高齢のペットにとって、見慣れた自宅は最も安心できる場所です。マルちゃんも、窓際のベッドで穏やかな時間を過ごすことができました。酸素室や皮下点滴といった医療ケアも、ご家族が自宅で実施できるようにサポートすることで、マルちゃんがストレスを感じることなくケアを受けることができました。
2. ご家族の負担を軽減しながらペットと向き合う時間を確保
在宅緩和ケアでは、ご家族が無理をせずに日常の中でケアを行うことができます。マルちゃんのケースでは、お母さんが一人で皮下点滴を行えるようトレーニングを行いました。その結果、ケアの時間が負担になることなく、ご家族はマルちゃんと向き合う時間を大切にすることができました。
3. 最期まで寄り添う選択肢を広げる
緩和ケアの目的は「治す」ことではなく、「苦痛を和らげる」ことです。ご家族がマルちゃんとともに過ごした時間は、医療的なケアだけではなく、心のケアでもありました。「最後まで一緒にいられてよかった」と感じていただけたのは、在宅緩和ケアを選んだからこそ実現できたことです。
8. わんにゃん保健室の取り組み:安心の在宅緩和ケアを提供
わんにゃん保健室では、ペットとご家族が安心して穏やかな日々を過ごせるよう、在宅緩和ケアのサポートに力を入れています。マルちゃんのケースのように、ご家族の想いに寄り添いながら、ペットにとって最善のケアを提供することを心がけています。
東京都を中心に、安心の往診サービスを提供
当院は東京都足立区をはじめ、東京23区や周辺地域を対象に往診を行っています。ご家族の状況やペットの性格を考慮し、自宅での診療や緩和ケアを行うことで、通院が難しいペットやご家族の負担を軽減します。
初めての往診でも安心のサポート体制
初めて往診を利用するご家族の中には、「どんな診療が受けられるの?」と不安を感じる方もいらっしゃいます。当院では、診療前に詳しいヒアリングを行い、ご家族のご希望やペットの状態をしっかりと確認。緩和ケアの流れを丁寧に説明し、不安なくサービスをご利用いただけるよう努めています。
大切な時間を一緒にサポートします
緩和ケアは、ペットとご家族が共に過ごす時間を穏やかにするためのケアです。マルちゃんのように、自宅で大好きなご家族と最後まで過ごせることは、ペットにとって何よりの安心です。
「在宅緩和ケアを考えているけれど、どうしたらいいかわからない」とお悩みのご家族も、まずはお気軽にご相談ください。ペットとご家族が少しでも笑顔で過ごせるよう、わんにゃん保健室が全力でサポートいたします。
最期まで愛するペットと穏やかな時間を過ごすために、わんにゃん保健室がお手伝いします。診療エリアやサービス内容については、ホームページやお電話でお気軽にお問い合わせください。
◆-----------------------------------◆
――――――――――――
【執筆・監修】
江本宏平(在宅緩和ケア専門獣医師)
【病院名】
往診専門動物病院 わんにゃん保健室
【診療受付】
10:00~19:00(不定休)
【住所】
東京都台東区松が谷3-12-4 マスヤビル
【連絡先】
03-4500-8701(留守電対応)
Mail:house.call@asakusa12.com
※診療中につき電話をとることができないことが多いです。
往診をご希望の際には、問合せフォームからご連絡をいただくか、留守番電話にメッセージをお残しください。
【SNS】
Instagram:
@wannyan_hokenshitsu(診療紹介)
@koheiemoto(家族に向けた心のケア)
note:
https://note.com/koheiemoto
【ご挨拶】
末期がん、腎不全、心疾患など、 高齢の犬や猫に対する在宅緩和ケア・ターミナルケアを専門としています。
ご自宅でのケアに限界を感じたとき、 病院への通院が難しくなってきたとき、
「最後まで苦しませたくない」という気持ちに寄り添った診療を行っています。
【診療対応地域(往診対応エリア)】
東京都:
23区全域、国立市、府中市、三鷹市、稲城市、調布市、狛江市、武蔵野市
神奈川県:
川崎市(高津区・宮前区・川崎区)、横浜市(青葉区・港北区・神奈川区・鶴見区)
埼玉県:
戸田市、川口市、草加市、蕨市、八潮市、三郷市
千葉県:
松戸市、市川市、浦安市、習志野市