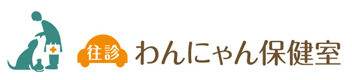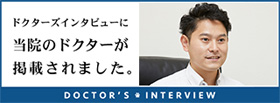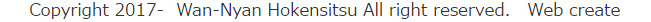猫の腎臓病は進行性の病気であり、高齢猫では避けて通れない問題の一つです。
初期の段階では目立った症状がないこともありますが、腎機能が低下すると、食欲不振や体重減少、嘔吐、歩行のふらつきなどの症状が現れ、最終的には緩和ケアが必要になります。
今回ご紹介する福ちゃん(日本猫・18歳・女の子)は、通院が難しい状況の中で腎不全ステージ4と診断されました。
ご家族は仕事と介護を両立しながら、在宅での緩和ケアを選択し、福ちゃんと最期まで穏やかな時間を過ごしました。
本記事では、福ちゃんの病気の進行や在宅緩和ケアの具体的な方法、最期の看取りまでの経過について詳しくご紹介します。
【目次】
- 腎臓病ステージ4とは?
- 腎臓病の初期症状と進行
- 在宅緩和ケアへの切り替え
- 日々のケア:投薬と皮下点滴
- 最期の1ヶ月の変化
- 呼吸のケア:酸素環境の整備
- ご家族の心の準備とサポート
- 旅立ちの日:福ちゃんが教えてくれたこと
- まとめ:在宅緩和ケアの意義
腎臓病ステージ4とは?
腎臓病は進行性の疾患であり、病気の段階(ステージ)によってケアの内容や必要な対応が大きく変わります。
福ちゃんが診断された腎臓病ステージ4は、最も進行した段階であり、腎機能の低下が顕著になり、体への影響も大きくなります。
腎臓病ステージ4の特徴
- 腎機能の大部分が失われ、体内の老廃物を適切に排出できなくなる
- 食欲低下や体重減少が進行し、全身の衰弱が目立つ
- 貧血が進行し、疲れやすく、動きが鈍くなる
- 嘔吐や下痢、脱水症状が見られることがある
- 多飲多尿の症状が悪化し、トイレに行く回数が増える
福ちゃんの場合も、診断の半年前から多飲多尿が目立ち始め、次第に体重減少や食欲不振が進行しました。
ご家族が「いつもなら自然と回復していたのに、今回はなかなか戻らない」と感じるようになり、最終的に往診を依頼されました。
診断のきっかけと初期の対応
福ちゃんは、1日1回以上の嘔吐と食欲廃絶を主訴に往診を受けました。
血液検査の結果、腎臓病ステージ4と診断され、すぐに在宅での治療とケアが開始されました。
- 嘔吐のコントロール(制吐剤の投与)
- 皮下点滴による水分補給の開始
- 食欲回復を目的とした栄養管理
- ご家族への在宅ケア指導
診断後、適切なケアを行うことで福ちゃんの嘔吐は完全に止まり、食欲も回復しました。しかし、腎臓病は完治しない病気であり、進行をできる限り遅らせることが重要となります。
腎臓病の初期症状と進行
腎臓病は進行がゆっくりであるため、初期の段階では目立った症状がないことが多く、ご家族が気づくころには病気がかなり進行しているケースも少なくありません。
福ちゃんも、初診の半年前から徐々に症状が出始めていましたが、「高齢だから仕方がない」と思い込み、様子を見ているうちに病状が進行していました。
多飲多尿と嘔吐:初期症状のサイン
腎臓病の初期に最もよく見られる症状の一つが「多飲多尿」です。
腎機能が低下すると尿が薄くなり、体が水分を補おうとするために水を大量に飲むようになります。福ちゃんも以下のような変化が見られました。
- 水を飲む量が明らかに増えた
- トイレに行く回数が増え、おしっこの量も多い
また、腎臓が正常に働かないことで体内に毒素が蓄積し、吐き気や嘔吐を引き起こします。
福ちゃんも、1日1回以上の嘔吐が見られ、「いつもなら1~2日で治まるのに、今回は長引いている」とご家族が心配されるようになりました。
腎臓病の進行が与える影響
腎臓病が進行すると、次のような症状が現れるようになります。
- 食欲不振(ご飯の匂いを嗅ぐが食べない、食べる量が減る)
- 体重減少(筋肉の減少が目立つ)
- 被毛のツヤがなくなる(毛並みが悪くなる)
- 元気がなくなり、寝ている時間が増える
- 歩行がふらつく、動きがゆっくりになる
福ちゃんの場合、初診時にはすでにこれらの症状が見られ、特に食欲低下と体重減少が顕著でした。血液検査の結果、腎不全の末期(ステージ4)と診断されました。
診断後の早急な対応
診断後は、病状の進行を少しでも抑えるために、以下の対応を行いました。
- 嘔吐のコントロール(制吐剤の投与)
- 食欲を回復させるための内服薬
- 皮下点滴の導入(水分補給と老廃物の排出を促進)
- 自宅でのケアの指導(投薬のコツ、食事管理)
これらの対応により、福ちゃんの嘔吐は完全に止まり、食欲も回復しました。とはいえ、腎臓病は完治する病気ではないため、継続的なケアが必要となります。
在宅緩和ケアへの切り替え
福ちゃんの腎不全がステージ4と診断された後、ご家族は動物病院への通院ではなく、在宅での緩和ケアを選択しました。
もともと福ちゃんはキャリーを見るだけで強く警戒し、通院が大きなストレスになってしまう猫でした。
そのため、ご家族は「最期までできるだけ穏やかに過ごさせたい」と考え、往診専門の動物病院に相談されました。
往診での診療開始
初診時、ご家族の希望として挙げられたのは以下の3点でした。
- できる限り通院せずに、自宅で診療を受けたい
- 無理に延命するのではなく、苦痛を軽減してあげたい
- 投薬や皮下点滴など、在宅でできるケアを知りたい
これらの希望を踏まえ、まずは福ちゃんの状態を詳しく把握するために、以下の検査・処置を行いました。
- 血液検査(腎機能、貧血の確認)
- 超音波検査(腎臓の状態、尿路の異常の確認)
- 皮下点滴の実施(脱水の改善)
- 嘔吐のコントロール(制吐剤の投与)
また、ご家族が自宅で行えるケアについても丁寧に説明し、すぐに実践できるよう指導を行いました。
日々のケア:投薬と皮下点滴
腎不全の進行を抑え、福ちゃんができるだけ快適に過ごせるようにするため、在宅での投薬と皮下点滴が重要な役割を果たしました。
特に、福ちゃんのように通院が難しい猫の場合、いかにストレスなくケアを継続できるかがポイントとなります。
投薬の工夫
福ちゃんはもともと警戒心が強く、直接投薬するのが難しい猫でした。
そのため、ご家族と相談しながら、できるだけ負担を減らせる方法を取り入れました。
- 苦手な薬はできる限り除外し、飲みやすい薬に調整
- 投薬用のおやつやカボチャに混ぜて与える
- 食欲が低下した場合は、無理に薬を飲ませるのではなく皮下点滴へ切り替え
この方法により、福ちゃんはストレスを感じることなく投薬を続けることができました。
皮下点滴の導入
腎不全が進行すると、体内の水分バランスが崩れ、脱水が進行しやすくなります。
福ちゃんも診断時には脱水が進んでいたため、皮下点滴を導入することになりました。
皮下点滴の頻度と方法
- 初期は2日に1回の頻度で実施
- ご家族が慣れてきた後、毎日夜の時間帯に実施
- できるだけリラックスできる環境で行う
ご家族の生活リズムに合わせ、焦らずにできる時間帯(仕事後の夜)に皮下点滴を実施することで、福ちゃんも安心してケアを受けることができました。
ご家族が工夫したポイント
- 最初は2人がかりで行い、慣れてきたら1人でもできるように練習
- 点滴後にご褒美として好きな食べ物を与える
このような工夫を取り入れることで、ご家族も無理なくケアを続けることができました。
最期の1ヶ月の変化
福ちゃんは腎不全のステージ4と診断されてから1年半、自宅での緩和ケアを続けながら穏やかに過ごしていました。
しかし、最期の1ヶ月に入ると、少しずつ病状が進行し、ご家族も変化を実感するようになりました。
食欲の低下と体重の減少
これまで工夫しながら続けていた食事も、最期の1ヶ月になると徐々に食べる量が減っていきました。
- 好きだったウェットフードも口にする機会が減った
- 一度に食べる量が減り、少しずつつまむ程度になった
- 体重が減少し、筋肉量の低下が目立つようになった
腎臓病が進行すると、体内の老廃物が排出されにくくなり、食欲が落ちることがよくあります。
福ちゃんのご家族も、「何か食べさせなきゃ」と焦る気持ちがありましたが、「無理に食べさせることが福ちゃんにとって本当に良いことなのか」を一緒に考えながらケアを進めました。
歩行のふらつきと体力の低下
最期の1ヶ月では、歩行のふらつきも目立つようになりました。
- トイレに行く途中で何度も休憩する
- 滑りやすい床では転倒することが増えた
- 普段の寝床から動かず、寝ている時間が増えた
ご家族は、福ちゃんの動きを見守りながら、トイレの近くに寝床を移動し、床には滑り止めマットを敷くなどの工夫をしました。
それでも福ちゃんは、最後まで慣れ親しんだトイレを使おうと頑張っていました。
呼吸状態の変化と酸素環境の準備
最期の1週間には、貧血も進行し、呼吸が浅く速くなることが増えてきました。
そのため、酸素室を準備し、苦しくなったときにすぐに対応できるようにしました。
- 福ちゃんが自分から酸素室に入ることはほとんどなかった
- ご家族がそばについて、酸素を鼻先に吹きかけることで対応
- 平日は仕事のため、基本的には酸素室で管理
「酸素室を準備する=お別れが近いのかも」と感じてしまい、ご家族も最初は戸惑っていましたが、福ちゃんの呼吸を楽にしてあげるためにできることの一つとして、前向きに取り入れることができました。
呼吸のケア:酸素環境の整備
腎臓病の終末期では、貧血や脱水の影響で呼吸が浅くなったり、速くなったりすることがあります。
福ちゃんも、最期の1週間に入ると呼吸の状態が悪化し、ご家族と相談しながら酸素環境を整えることになりました。
酸素室の準備
まず、ご家族が在宅でできる対策として、酸素発生装置を導入しました。
- 酸素発生装置を1台設置
- 専用の酸素室を用意し、福ちゃんが落ち着ける環境を確保
- ご家族が不在のときは、酸素室内で管理
しかし、福ちゃんは酸素室に入ることを嫌がり、自分のベッドで過ごすことを選びました。
そのため、ご家族が在宅のときは、鼻先に酸素を吹きかける方法を取りました。
酸素環境の工夫
ご家族と相談し、福ちゃんの負担にならないよう、できる限り自然に酸素を取り入れられるよう工夫しました。
- 窓際のベッドの近くに酸素チューブを設置
- 寝ている間に酸素が届くように調整
- ご家族がそばにいるときは、手で酸素を鼻先に送る
酸素を取り入れることで、福ちゃんの呼吸は少し落ち着き、苦しそうな時間を減らすことができました。
ご家族の心の準備
「酸素を使う」という選択は、ご家族にとって「もうお別れが近いのではないか」という不安を抱かせることもあります。
しかし、酸素はあくまで「今、少しでも楽に過ごしてもらうためのケア」です。
福ちゃんのご家族も、最初は戸惑いながらも、できることを一つずつ取り入れていきました。
最期の1週間:福ちゃんとご家族の時間
福ちゃんの最期の1週間は、ご家族にとってかけがえのない時間となりました。
食欲がなくなり、動くことが少なくなっても、ご家族のそばで穏やかに過ごす姿がありました。
食事と水分摂取の変化
最期の1週間に入ると、福ちゃんはほとんど食事を摂らなくなりました。
- お水は少しずつ飲むが、ご飯はほとんど食べない
- 無理に食べさせることはせず、好きなものをそっと差し出す
- たまに興味を示して、ほんのひと口だけ食べることもあった
ご家族は、「食べてくれないことが不安」と感じながらも、無理に与えることはせず、福ちゃんの意思を尊重する選択をされました。
最後まで自分で歩こうとする姿
福ちゃんは最期の1週間、寝ている時間がほとんどでしたが、それでもトイレには自力で行こうとしました。
- ふらつきながらも、トイレまで少しずつ歩く
- 途中で休憩を挟みながら、ゆっくりと進む
- 滑らないように床にはペットシーツと滑り止めマットを敷いた
ご家族は、福ちゃんの動きを見守りながら、できる限り手を貸さず、「自分でやりたい」という気持ちを尊重しました。
最後の夜:福ちゃんが選んだタイミング
福ちゃんは、ご家族が仕事で不在になる日を前に、旅立ちのタイミングを自分で選んだかのように、最期の時を迎えました。
翌日、ご家族は「福ちゃんが私たちを待っていてくれたのかもしれない」と話されていました。
出張の日を避け、家族全員が揃う日に旅立った福ちゃんの姿に、ご家族も「しっかりお別れを言う時間をくれた」と感じたそうです。
福ちゃんの旅立ちとご家族の想い
福ちゃんは、家族が揃う最後の夜に穏やかに旅立ちました。
その瞬間、ご家族は「ついにこの時が来たんだ」と静かに受け止めるしかありませんでした。
しかし、悲しみの中にも、「福ちゃんが最後まで頑張ってくれたこと」「しっかりと見送ることができたこと」への感謝の気持ちがありました。
福ちゃんが残してくれたもの
初めての在宅での看取りを経験したご家族にとって、福ちゃんの存在は何よりも大きなものでした。
通院がどうしても苦手だった中、それでも最期まで緩和できたことが、ご家族にとって、最後に福ちゃんにしてあげられた恩返しだと話されていました。
最期まで自分のペースで生き抜き、そして家族全員が揃ったタイミングで旅立ってくれたことに、感謝しかないとのことでした。
在宅での看取りを選んで
今回、ご家族は「できるだけ福ちゃんにとって負担の少ない最期」を目指し、在宅での緩和ケアを選択しました。
その決断が、福ちゃんにとっても、ご家族にとっても、後悔のないものになったと感じています。
- 最期の時間を大好きな家で過ごすことができた
- 無理に病院へ連れて行かず、穏やかに過ごせた
- 福ちゃんの気持ちを尊重しながらケアができた
ご家族は、「福ちゃんのために、最善の選択ができたと思います」と話されていました。
これから看取りを迎えるご家族へ
ペットの最期をどう迎えるかは、ご家族にとって大きな決断です。
病院での治療を続けるか、自宅で穏やかに見守るか、正解は一つではありません。
しかし、どの選択をしても、「その子が少しでも苦しくないように」と願う気持ちは共通しているはずです。
福ちゃんのご家族のように、「自宅で穏やかに看取りたい」と考える方も多いでしょう。
そんな時は、在宅緩和ケアという選択肢があることを思い出してください。
ご家族が後悔しないよう、一緒に考えていくことが大切です。
在宅緩和ケアを支えるわんにゃん保健室
私たち、わんにゃん保健室は、ペットが最期まで安心して過ごせるように、ご家族と一緒に在宅緩和ケアを支えています。
「病院に連れて行くのが難しい」「できるだけ自宅で看取りたい」——そんなご家族の想いに寄り添い、往診という形でサポートを行っています。
在宅緩和ケアでできること
病院への通院が難しくなったペットでも、ご自宅で適切なケアを続けることが可能です。
わんにゃん保健室では、以下のようなサポートを提供しています。
- 状態に応じた治療・ケアの提案(内服薬の調整、皮下点滴、栄養管理など)
- ご家族ができるケアの指導(皮下点滴の方法、投薬のコツ、環境調整のアドバイス)
- 急な変化への対応(呼吸困難時の酸素環境構築、緩和ケアの進め方)
- ターミナルケアのサポート(最期の時間の過ごし方、看取りの準備)
診療エリアについて
現在、わんにゃん保健室では、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の一部地域にて往診対応を行っています。
「在宅緩和ケアを考えている」「どのように進めればいいかわからない」といったお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
あなたと大切なペットのために
在宅緩和ケアは、ご家族が愛するペットの最期の時間を穏やかに見守るための選択肢のひとつです。
福ちゃんのご家族のように、「できるだけストレスの少ない環境で過ごさせてあげたい」と思われている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
どんな小さなことでも構いません。私たちが、一緒に最適なケアの方法を考えていきます。
まずは、お電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
まとめ
福ちゃんのケースを通して、腎不全の最終段階における在宅緩和ケアの大切さをお伝えしました。
- 腎不全の進行に合わせた適切なケアが重要
- 食欲や歩行の変化に対して、無理のないサポートを
- 呼吸状態の悪化時には、酸素環境の準備を
- 最期の時間をご家族と共に過ごせるよう、ターミナルケアを検討
- 在宅緩和ケアは、ご家族の不安を軽減し、後悔のない選択につながる
大切な家族の一員であるペットが最期の時を迎えるとき、ご家族が安心して見守れるよう、わんにゃん保健室はサポートを続けていきます。
◆-----------------------------------◆
――――――――――――
【執筆・監修】
江本宏平(在宅緩和ケア専門獣医師)
【病院名】
往診専門動物病院 わんにゃん保健室
【診療受付】
10:00~19:00(不定休)
【住所】
東京都台東区松が谷3-12-4 マスヤビル
【連絡先】
03-4500-8701(留守電対応)
Mail:house.call@asakusa12.com
※診療中につき電話をとることができないことが多いです。
往診をご希望の際には、問合せフォームからご連絡をいただくか、留守番電話にメッセージをお残しください。
【SNS】
Instagram:
@wannyan_hokenshitsu(診療紹介)
@koheiemoto(家族に向けた心のケア)
note:
https://note.com/koheiemoto
【ご挨拶】
末期がん、腎不全、心疾患など、 高齢の犬や猫に対する在宅緩和ケア・ターミナルケアを専門としています。
ご自宅でのケアに限界を感じたとき、 病院への通院が難しくなってきたとき、
「最後まで苦しませたくない」という気持ちに寄り添った診療を行っています。
【診療対応地域(往診対応エリア)】
東京都:
23区全域、国立市、府中市、三鷹市、稲城市、調布市、狛江市、武蔵野市
神奈川県:
川崎市(高津区・宮前区・川崎区)、横浜市(青葉区・港北区・神奈川区・鶴見区)
埼玉県:
戸田市、川口市、草加市、蕨市、八潮市、三郷市
千葉県:
松戸市、市川市、浦安市、習志野市