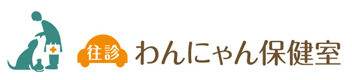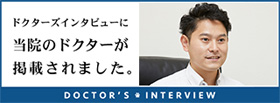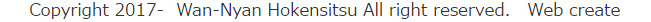猫の心筋症(特に肥大型心筋症など)は、高齢猫に比較的多い病気であり、診断されたときには「いつ何が起こるかわからない」という不安に包まれてしまうこともあります。
「通院での検査や処置が難しくなってきたけれど、このままで大丈夫?」
「呼吸が苦しそうに見えるけれど、どうすればいいの?」
「最期まで家で穏やかに過ごさせてあげたいけど、それって現実的なの?」
そんな不安を抱えるご家族に向けて、この記事では心筋症におけるターミナルケアの考え方、在宅でできる具体的なサポート、そして治療から緩和への切り替えのヒントを、獣医師の立場からわかりやすくお伝えしていきます。
猫の心筋症とは?──はじめに理解しておきたいこと
猫の心筋症は、心臓の筋肉(心筋)に異常が生じることで、心臓の機能が低下する病気です。中でも「肥大型心筋症(HCM)」は猫にもっとも多く、心筋が厚く硬くなることで血液の循環が悪くなります。
初期には無症状のことも多いため、「気づいたときにはすでに進行していた」というケースも少なくありません。心筋症と診断されたときに、病気の性質を正しく知ることは、今後のケアの選択にもつながります。
心筋症の種類と特徴(特に肥大型)
猫の心筋症にはいくつかのタイプがありますが、なかでも肥大型心筋症(HCM)は特に多く見られます。
☑︎ 心筋が肥厚して心室内が狭くなる
☑︎ 血液がうまく送り出せず、全身に十分な酸素が行き渡らない
☑︎ 最終的には肺に水がたまる「肺水腫」や「胸水」が起こることもある
このように、呼吸や循環に大きく影響を与える病気です。
よくある症状と見逃しやすいサイン
心筋症の症状は、必ずしも急激に出るとは限りません。次のような変化があった場合は注意が必要です。
☑︎ 呼吸が早くなる、浅くなる(休息時も口呼吸など)
☑︎ 階段を登れない・ジャンプしないなどの活動性の低下
☑︎ 急に後ろ足を動かせなくなる(血栓塞栓症)
「少し疲れてるのかな?」という程度に見えることもあるため、慎重な観察が必要です。
診断されたとき、まず大切にしたいこと
心筋症と告げられたとき、最初は動揺するかもしれません。でも、以下のことをまず確認しておくと、その後のケアの選択がスムーズになります。
☑︎ 呼吸状態は安定しているか?(今すぐ酸素が必要かどうか)
☑︎ 内服薬の開始が必要か?飲ませられるか?
☑︎ 今後の急変に備えてどんな選択肢があるか
病名を知ることは、ゴールを定めるための第一歩です。次は「心筋症=すぐに亡くなる」という誤解について、正しい理解をお伝えします。
「すぐに亡くなる病気」ではありません
心筋症と診断された直後、多くの飼い主さんが「この子はもうすぐ亡くなるの?」と不安になります。
もちろん、急変や突然死のリスクがある病気ではありますが、それが“すぐ”という意味ではありません。症状を観察し、適切なケアを行えば、しばらく落ち着いて過ごせるケースも多くあります。
急変=すぐ死に至るとは限らない
たしかに心筋症は急激な症状悪化(肺水腫や血栓など)を引き起こすことがありますが、「急変 = 即死」ではないことも多いのです。
☑︎ 呼吸が速くなる、苦しそうになる前に前兆がある
☑︎ 一度落ち着けば、数日~数週間安定することもある
☑︎ 「あのときこうしていれば」という後悔を減らすためにも観察が大切
治療によって維持できる期間もある
投薬や酸素ケアによって、呼吸や循環を安定させることが可能な場合もあります。無理に延命をするのではなく、「その子らしく過ごす」ことを目指した治療が、QOLを高めてくれます。
☑︎ 利尿剤や強心薬の使用で症状をコントロール
☑︎ 食欲や活動性を保ちながら過ごす子も多い
☑︎ 完全には治せないが「うまく付き合う」ことはできる
在宅での見守りでできるサポート
通院が難しい猫でも、在宅での観察とサポートを工夫することで、穏やかな日常を取り戻すことができます。
☑︎ 呼吸のチェックや、安静にできる環境づくり
☑︎ 必要に応じた往診や在宅酸素の導入
☑︎ ご家族の「気づき」が命を支える大きな力になる
焦らず、ひとつひとつのサインに気づくことが、これからの時間をより良いものにしてくれます。
次は、内服薬が難しいときに選択できる「注射薬+皮下点滴」というケアについてお話しします。
内服が難しいときの代替手段
心筋症の治療では、内服薬が重要な役割を果たしますが、「薬を飲ませるのが難しい」「毎日の投薬が猫にも家族にも負担になっている」というご相談をよくいただきます。
そんなときに検討したいのが、注射薬への切り替えや皮下点滴による投与です。薬を「飲ませる」のではなく「体に入れる」方法を工夫することで、治療の継続と猫の穏やかな生活を両立できることがあります。
シリンジ投薬がストレスになる場合
元気がない、口を開けさせるのが難しい、嫌がって暴れる…。そんな状態で毎日お薬を飲ませることは、ご家族にも猫にも大きなストレスになります。
☑︎ 投薬のたびに関係性が悪くなってしまう
☑︎ 無理に口をこじ開けると、呼吸を乱す原因にも
☑︎ 飼い主さんが「怖くてできない」と感じることもある
注射薬+皮下点滴での投与という選択肢
猫の状態やご家族の生活に合わせて、薬剤を皮下点滴の中に混ぜて投与する方法があります(例:利尿剤、制吐剤、鎮痛薬など)。これにより、口からの投薬を減らすことができます。
☑︎ 注射によって安定的な投与が期待できる
☑︎ 家でのケアがシンプルになり、精神的な余裕が生まれる
☑︎ 通院が難しい場合の代替手段として有効
なお、投与量や組み合わせには注意が必要なので、必ず獣医師の指導のもとで行いましょう。
ご家族が無理をしないケア設計の重要性
「投薬を続けなければ」とがんばる気持ちは尊いものですが、無理を重ねてしまうとご家族の心も疲れてしまいます。
☑︎ ケアは「正しさ」より「続けられるかどうか」が大切
☑︎ 家族が笑顔でいられることが、猫にとっても安心につながる
☑︎ 無理せず続けられる方法を、一緒に見つけていきましょう
次は、心筋症に多くみられる「胸水」の問題と、その対応についてお伝えします。
胸水抜去の正しい理解と注意点
心筋症が進行すると、心臓のポンプ機能が低下し、胸の中に水がたまる「胸水」が起こることがあります。胸水が増えると肺が圧迫され、呼吸が浅く速くなり、猫は苦しそうに見えるようになります。
このような状態に対して行うのが「胸水抜去」という処置ですが、すべてのケースにおいて行うべきとは限りません。ここでは、胸水抜去について正しく理解し、必要性と負担を見極めるヒントをお伝えします。
胸水がたまるとどうなる?
胸水は、心臓や血管からしみ出した体液が胸腔内にたまったものです。肺が圧迫されてうまく膨らまなくなることで、呼吸がしにくくなります。
☑︎ 安静時にも呼吸が浅く速くなる
☑︎ 寝ているときに「横向き」になれず座ったままになる
☑︎ 酸素室を使っても改善しない場合は注意が必要
このような症状があれば、胸水の可能性も視野に入れる必要があります。
抜去処置のメリットと身体的負担
胸水を抜くことで肺が広がり、呼吸が一気に楽になることがあります。ただし、処置には注射針を刺す必要があり、猫にとっては少なからず痛みや緊張を伴います。
☑︎ 呼吸状態が急速に改善するケースもある
☑︎ 一方で、針を刺す処置には苦痛や不快感がある
☑︎ 抜いてもすぐに再貯留する場合もある
何度も繰り返すことが猫の負担になっている場合は、あえて抜去を控える判断も考えられます。
苦痛を伴う場合の判断と緩和的ケアへの切り替え
処置によって一時的な改善が見込めても、それが猫にとって「つらい体験」となっているなら、無理に続けることが最善とは限りません。
☑︎ 何度も胸水を抜くより、酸素や薬剤での緩和を優先する
☑︎ ご家族の意思と猫の様子をふまえて治療方針を柔軟に見直す
☑︎ 穏やかに過ごすことが、何よりのケアになることもある
次は、呼吸を助けるために必要な「在宅酸素ケア」について、導入のポイントや注意点をご紹介します。
在宅酸素はどう整える?
呼吸がつらそうな猫にとって、「酸素を吸える環境を整えること」は命をつなぐだけでなく、日々の安心にもつながります。在宅でも酸素環境を整えることは可能です。
ここでは、在宅酸素の導入方法や使用上の注意点についてご紹介します。
在宅酸素の準備に必要なもの
猫に酸素を届ける方法はいくつかありますが、多くの場合は「酸素濃縮器+酸素ハウス」を使用します。
☑︎ 酸素濃縮器(電源が必要)
☑︎ 密閉性のあるケージやテント(酸素ハウス)
☑︎ 万一の停電に備えたバックアップ手段(酸素ボンベやポータブル電源)
酸素濃縮器はレンタルが可能で、動物病院や専門業者を通じて自宅に設置できます。
設置時の注意点とトラブル回避
酸素ハウスを快適な空間にするためには、温度や湿度、音、ストレス対策も大切です。
☑︎ 濃縮器の作動音が猫のストレスにならないように設置場所を工夫
☑︎ 温度管理(夏場の酸素ハウス内は熱がこもりやすい)
☑︎ 密閉しすぎると酸素がこもってしまうため、適度な換気も必要
猫が安心して入ってくれるよう、日頃から「落ち着ける場所」として慣れさせることも大切です。
導入の判断は獣医師と相談を
酸素の導入は、すべての心筋症の猫に必要というわけではありません。症状や呼吸状態、今後の方針に応じて判断することが大切です。
☑︎ 呼吸が苦しそう、動かなくなってきた場合はすぐ相談を
☑︎ 酸素が必要なレベルかどうか、診察での確認が重要
☑︎ 導入後も酸素濃度や状態を定期的にチェックしましょう
次は、呼吸だけでなく「ごはんが食べられないとき」のケアについてお伝えします。
ごはんが食べられないときの対応
心筋症が進行してくると、息が苦しくて「食べたいのに食べられない」状態になることがあります。これは「食欲がない」のではなく、体がつらくて食事がとれないケースも多いのです。
ここでは、そんなときにできる工夫やサポートをご紹介します。
呼吸が安定すると食欲も戻ることがある
食欲の低下が、単に病気の末期だからというわけではなく、呼吸の苦しさが原因であることも多いです。呼吸が落ち着くことで、自然と食べ始めることもあります。
☑︎ 酸素室や利尿剤で呼吸が落ち着いたら少しずつ食べ始める
☑︎ 横になる姿勢が取れるようになると、食事への意欲も回復しやすい
☑︎ 吐き気止めなどを併用することで、食べやすくなることもある
強制給餌は慎重に
「食べてほしい」という思いから強制的に口へ運んでしまうと、猫にとっては大きなストレスとなることがあります。
☑︎ 呼吸が苦しい状態では、無理な給餌は逆効果になる
☑︎ 無理に与えることで食事そのものを嫌がってしまう可能性も
☑︎ 「今日はこれくらいで大丈夫」と一歩引く勇気も必要
食べやすい工夫とケアのバランス
無理に「食べさせる」のではなく、「食べやすくしてあげる」工夫を心がけましょう。
☑︎ ウェットフードやスープ状のごはんに変える
☑︎ 手のひらに乗せてみる/横に寝たまま食べられる工夫を
☑︎ 少量ずつ何度も、を意識する(1回の完食にこだわらない)
「今この子が何をつらいと思っているのか」を見つめながら、食事のサポートも無理なく続けていきましょう。
次は、猫にとっての「穏やかな最期とは何か」について考えていきます。
穏やかな最期とは?
病気の進行とともに、「延命」から「看取り」へとケアの視点が変わっていく時期があります。 その中で、ご家族にとって最も大切なのは「この子にとって何が幸せなのか」を見つめ直すことです。
ここでは、穏やかな最期を迎えるための考え方や、家族ができるサポートについてお伝えします。
治すことよりも「苦しくない」が大切になる
最期の時間においては、治療よりも「痛みや苦しさを取り除く」ことが最優先になります。
☑︎ 無理な検査や処置は控え、安心できる環境を整える
☑︎ 苦しみのサイン(呼吸、体勢、鳴き方)を見逃さない
☑︎ 「この子らしさ」を大切にした関わり方を意識する
そばにいることが、何よりの薬になる
体に触れる、声をかける、一緒に過ごす…。特別なことをしなくても、ご家族の存在は猫にとって大きな安心になります。
☑︎ 「そばにいてくれる」ことが猫の心を落ち着かせる
☑︎ 抱っこよりも、隣にそっと座るだけで十分なこともある
☑︎ 眠るように旅立てる子の多くは、家族の声を聞きながら過ごしている
「良いお別れだった」と思えるように
後悔をゼロにするのは難しいかもしれません。でも、「最期をどう迎えたか」は、ご家族の心を大きく支えてくれるものになります。
☑︎ 「あのときこうしてよかった」と思える場面を増やす
☑︎ できなかったことより、できたことを大切に
☑︎ 悲しみの中にも、あたたかな記憶を残せるお別れを目指しましょう
次はいよいよ最終章、「治療から看取りへ、気持ちの切り替え方」についてお話しします。
治療から看取りへ、気持ちの切り替え方
「もう治せないのかもしれない」と感じたとき、胸がしめつけられるような不安や迷いが生まれます。 でもその気持ちは、愛情があるからこそ。ここでは、治療から緩和ケア・看取りへと気持ちを切り替えるヒントをお届けします。
「やめる」のではなく「切り替える」だけ
治療を終える=あきらめる、ではありません。ケアの目的が「治すこと」から「楽にすること」へ変わるだけです。
☑︎ 投薬や処置を減らすことで、穏やかな時間を増やせる
☑︎ 「最後までケアしてあげたい」という思いが支えになる
☑︎ ケアの主役は「命を守ること」から「痛みを減らすこと」へ
正解はひとつじゃない
どんな選択をしても、それはご家族がその子のために悩み、考えた結果です。 「これでよかったんだ」と思える選択肢は人それぞれ違っていて当然です。
☑︎ 他の人と比べる必要はない
☑︎ ご家族が納得できる道を選ぶことが一番大切
☑︎ 自分を責めすぎないで、「いまのこの子の気持ち」に耳を傾けて
看取りを通して気づく“あたたかさ”
最期の時間は、決して悲しいだけのものではありません。 そこには、言葉にできないあたたかさや、絆の深さがあるはずです。
☑︎ 小さな変化を見つけて声をかけるたび、通じ合う感覚が生まれる
☑︎ そばにいることが、自分自身の癒しにもなる
☑︎ 最期まで一緒にいられた時間が、これからの人生の支えにもなる
ここまでお読みくださり、ありがとうございました。 次は、このテーマのまとめに入ります。
まとめ|心筋症と診断された猫と、穏やかに向き合うために
猫の心筋症は、初期の段階ではあまり症状が目立たないことも多く、 「急に苦しそうになった」「病院に行ったら末期だった」と驚かれる飼い主さんも少なくありません。
ですが、心筋症=すぐに亡くなるわけではありません。
✔︎ 内服が難しいときには、注射や皮下点滴での投薬に切り替える選択肢もあります。
✔︎ 胸水抜去がつらい処置である場合は、あえて控える判断もあります。
✔︎ 在宅での酸素ケアを整えることで、病院ではなく「おうちで過ごす時間」を叶えることも可能です。
いまこの瞬間から「何をしてあげられるか」を見つめ直すこと、
そして、治療から穏やかな看取りへと視点を変えることは、 決して“諦め”ではなく、愛情にあふれた選択です。
「最期まで寄り添えた」と思える時間を、一緒につくっていきましょう。
猫の心臓病や呼吸の変化が不安なときは、ご相談ください
呼吸が浅くなってきた/ごはんを食べられない/通院が難しくなってきた――
そんなときは、一人で抱え込まずにご相談ください。 往診専門動物病院わんにゃん保健室では、 猫の心筋症や終末期のケアに寄り添った在宅サポートを行っています。